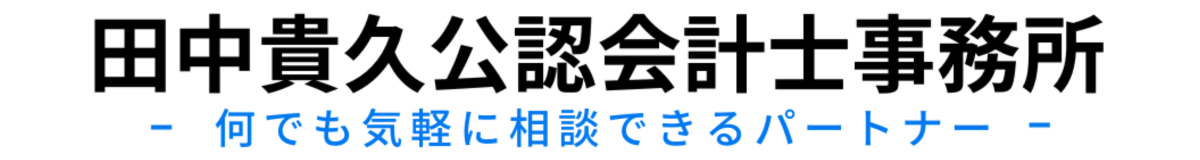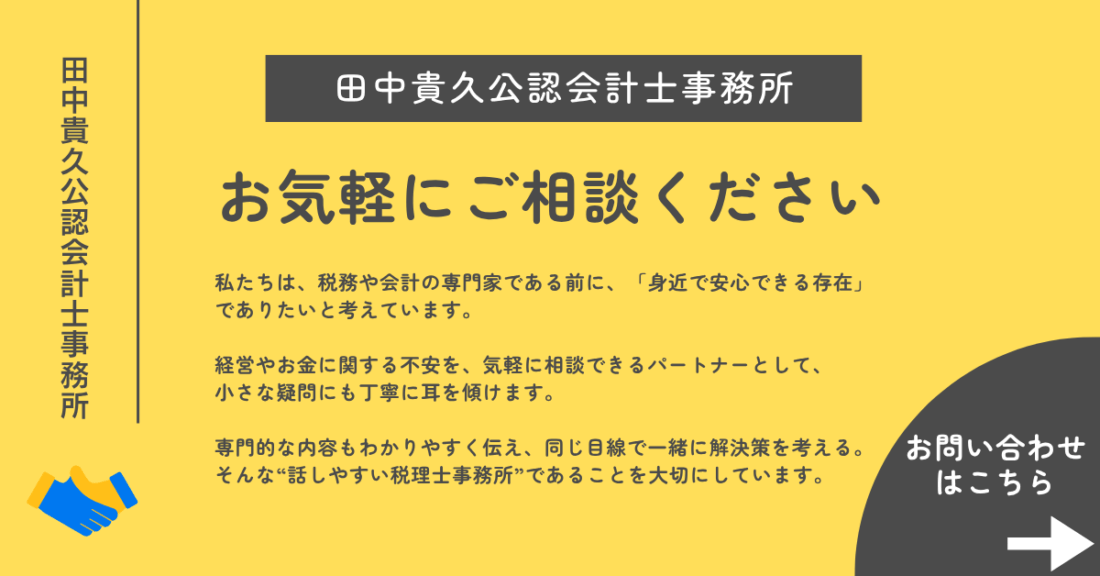メロンブックスで売上が出てきたものの、確定申告が必要なのか判断できない人も多いでしょう。
この記事では、売上がいくらから確定申告が必要なのか、確定申告をする場合の手順や、メロンブックスの売上を確定申告する際によくある疑問について解説します。
メロンブックスの売上は確定申告が必要?働き方で基準をチェック
メロンブックスの売上について、確定申告の対象となるかは所得の額で決まります。所得とは、売上から経費を引いた金額のことです。
所得の額が一定額を超えると確定申告が必要になりますが、基準額は作家としての活動が副業か本業かで異なります。
ここでは、副業と本業それぞれの場合に分けて解説します。
副業の場合
会社員やパートなどで働いており、年末調整を受けている場合、メロンブックスでの作家活動は税務上は副業となります。
副業となる場合、メロンブックスからの年間所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
注意点として、メロンブックス以外にも所得がある場合は、それらもすべて合算して20万円を超えるかで判定します。給与所得以外の所得合計が20万円を超えている場合は確定申告が必要、と覚えておきましょう。
仮にメロンブックスでの販売活動が一時的でも、その年中に稼いだ所得が20万円を超えていれば確定申告をする必要があります。
本業の場合
作家活動が本業の場合、メロンブックスを含めた年間の所得金額が95万円を超えると確定申告が必要です。
確定申告では要件を満たした人は「所得控除」が受けられます。所得額が少なくなるとそれだけ税額を下げられるため、どのような控除が適用できるのかを確認しておきましょう。
所得控除を受けた結果、所得が0円となれば確定申告は必要ありません。
なお、所得控除のうち、所得2,500万円以下であれば誰でも受けられる「基礎控除」があります。基礎控除額は所得に応じて変動しますが、所得額が132万円以下であれば95万円の控除を受けられます。
メロンブックスで得た収入の確定申告の手順3ステップ
メロンブックスで得た収入を確定申告する手順を、3つのステップにわけて解説します。
1.収入と支出を把握する
まず、1年間の収入と支出を把握する必要があります。
メロンブックスのサークルポータルから売上集計と棚卸データをダウンロードし、収入と売れ残った在庫を確認しましょう。合わせて、経費の領収書やレシートを整理します。
経費として計上できるのは、作家活動に直接関係する支出のみで、原則として領収書や請求書が必要です。特に年末の売上や経費は、明細書などのデータ反映が翌月になる場合があるため、計上漏れがないように注意が必要です。
なお、売上や経費のデータ、紙資料は保存しておく必要があり、期間は書類の種類によって異なるものの、7年間保存しておくと安全です。
2.確定申告書を作成する
1年間の売上や経費、自身が適用できる控除を把握したら、確定申告書を作成します。
確定申告書は書面で作成する方法と、オンラインのツールや確定申告ソフトを使って作成する方法があります。
確定申告書の作成には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利です。指示にしたがって入力するだけで、簡単に確定申告書が作成できます。
また、民間の確定申告ソフトも同様で、指示通りに入力すると確定申告書の作成が可能です。
本業がある人は、職場から受け取った「源泉徴収票」の内容を忘れずに転記してください。
3.税務署へ提出する
確定申告書の提出方法にはe-Taxによる電子申告、紙での郵送、税務署窓口に持参する方法の3つがあります。e-Taxは自宅で申告が完結する便利な方法のため、おすすめです。
確定申告書を作成したら、期限内に自身が住んでいる地域の所轄税務署に提出し、納税までを完了させます。
確定申告書の提出と納税は期限が同じで、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。期限内に納税までを終わらせないと、追徴課税が発生するため、必ず期限を守りましょう。
メロンブックスで得た収入から差し引ける支出例
メロンブックスの作家活動で得た収入から差し引ける経費には、全額計上できるものと、一部のみ計上できるものがあります。経費を計上すると所得が減り節税につながりますが、経費にできるのは作家活動に直接関係する支出だけです。
ここでは、計上できる経費と勘定科目について解説します。
全額計上できる経費
全額計上できる経費と、対応する科目は下記のとおりです。
| 経費 | 対応する科目 |
|---|---|
| 印刷代 | 印刷費 |
| 画材・ソフト購入費 | 消耗品 |
| 参考資料の本 | 新聞図書費 |
| イベント出展料 | 広告宣伝費 |
| 打ち合わせの飲食 | 会議費 |
| 電気代 | 水道光熱費※ |
| 家賃 | 地代家賃※ |
| メロンブックスの手数料 | 支払手数料 |
※電気代や家賃を全額経費にできるのは、事務所や作業場が自宅以外で、プライベートでの使用と分かれている場合です。プライベートでも使用している場合は、按分計算が必要になります。
1つあたりの10万円を超える画材やソフトなどを購入した場合、一度に全額を経費にはできず、固定資産として毎年定額を経費として計上する必要があります。
また、作品の参考資料として買ったフィギュアや本は経費にできますが、趣味で買ったものは経費にできないことを覚えておいてください。
なお、白紙の領収書に書きこんで架空の経費を計上するのは、脱税行為にあたるため絶対にしてはいけません。
按分が必要な経費
自宅の一部を作業スペースにしている場合の家賃や光熱費は、作業分のみ経費計上できます。このように、プライベートと事業の両方に関わる支出を、合理的な基準で分ける計算を「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
たとえば、作業スペースとして使っている面積とプライベートで使っているスペースの面積で按分する、作業時間を記録してその時間で按分するなどの方法があります。
いずれにしても、後で税務調査が入った場合に、調査員に説明できる合理的な基準で按分することが必要です。
青色申告を活用した節税
メロンブックスの売上を「事業所得」として「青色申告」で確定申告すると、最大65万円の所得控除が受けられるなど、大きな節税効果を得られます。
恩恵が大きいため、対象となる人はぜひ活用しましょう。
メロンブックスの売上を事業所得にする
青色申告をするには、メロンブックスの売上が「事業所得」として認められる必要があります。
作家活動が事業として継続的に行われていないと認められないため、帳簿書類を保存しているか、赤字解消の取り組みをしているかなどが判断基準となります。
副業であっても、このような要件を満たせば事業所得として申告可能です。事業所得と認められない場合は「雑所得」となり、青色申告はできません。
なお、副業での収入が300万円以下かつ本業の10%未満の稼ぎしかない場合も、事業所得とは認められない可能性があります。
事前に青色申告の届出を提出する
青色申告をするためには、青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以降に開業したのであれば、開業日から2か月が期限になります。
また、申請書を出す前には「開業届」の提出が必要です。開業届を提出するタイミングで所得税の青色申告承認申請書を一緒に提出するとスムーズです。
青色申告に必要な書類で確定申告する
青色申告では、「所得税青色申告決算書」として損益計算書とその内訳、貸借対照表を提出する必要があります。
簡易な帳簿を作成して確定申告した場合は10万円の控除、複式簿記で確定申告をした場合は55万円の控除が受けられます。複式簿記かつe-Taxで申告すると、65万円の控除が適用されます。
メロンブックスの売上を確定申告する人からよくある質問
メロンブックスの売上に関する確定申告で、よくある質問に回答します。
販売手数料はどのように計上すべきですか?
販売手数料は「支払手数料」として経費に計上し、売上は販売手数料が引かれる前の総額で計上します。
仕訳は下記のとおりなので、参考にしてください。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 7,000 | 売上10,000 |
| 支払手数料3,000 |
確定申告する際は振り込まれた手取額を売上としないように注意し、販売手数料が引かれる前の売上と、販売手数料の両方を計上する必要があります。
売れ残った本は計上する必要がありますか?
12月31日時点で売れ残った在庫は経費に計上できず、「棚卸資産」として貸借対照表の資産に計上します。
メロンブックスのサークルポータルなどで棚卸在庫を確認し、いくら売れ残っているかを確認しましょう。
在庫分の仕入や印刷費を経費に含めている場合は、期末に棚卸資産に振り替える処理が必要です。この処理を忘れると、経費の過大計上として追徴課税の対象になるため、確定申告の際は忘れないようにしてください。
まとめ

メロンブックスの売上に関する確定申告は、ポイントを押さえれば自分ですることも可能です。確定申告直前に一気にやろうとすると負担が大きくなるため、早めに準備を始めることで、スムーズに申告を終えることができます。
ただし、青色申告で65万円控除を目指す場合や、経費計上に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、正しく節税できるため、税務上のリスクを減らせます。
田中貴久公認会計士事務所は、クリエイターの確定申告に豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。