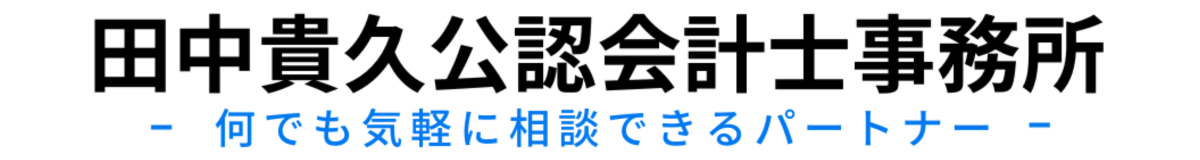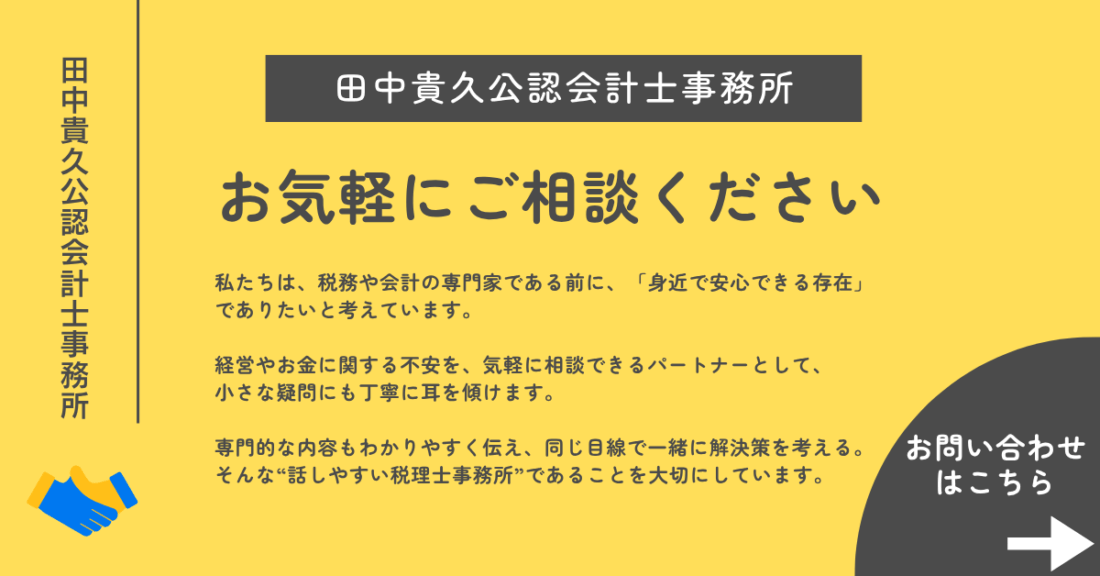漫画家として活動していると、原稿料から「源泉徴収」として税金が引かれていることに疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。また、引かれた分が戻ってくる可能性があると聞いても、「確定申告が難しそう」と感じる方も多いはずです。
本記事では、源泉徴収の仕組みから節税方法までをやさしく解説します。
そもそも源泉徴収とはどういう仕組み?
そもそも源泉徴収とはどのような仕組みでしょうか。また、源泉徴収で徴収される金額はどれくらいなのでしょうか。その基本的な仕組みと源泉徴収される金額について確認しましょう。
源泉徴収の仕組み
源泉徴収は所得税の支払いに関する制度です。まず会社が個人に給与や報酬を支払う際に、所得税を納めるための一定額を差し引きます。会社は個人に代わってこれを国に納付します。年末に所得が確定した段階で、過不足を精算し、足りない分を納める・払い過ぎていた分を還付するのが源泉徴収の基本的な仕組みです。
この源泉徴収は所得税を確実に徴収するための方法で、法人が勤務している労働者や個人相手に報酬を支払った際に行われます。
会社員の場合は年末調整で、個人の場合には確定申告で過不足分の精算が行われます。その際に年末に会社より発行される、「源泉徴収票」(給与所得など)「支払調書」によって源泉徴収された金額を確認することができます。
対象となる報酬
源泉徴収の対象には、原稿料・印税のほか、謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象です。
昨今クラウドファンディングで漫画家が支援金を得ることがありますが、投資型クラウドファンディングの場合には源泉徴収がされます。
漫画家の場合、原稿料や印税が源泉徴収の対象となるため、報酬は源泉徴収されます。そして、確定申告の際に源泉徴収された所得税について過不足分の精算を行います。つまり、源泉徴収分だけでは納めきれていない場合には追加で納税し、源泉徴収された金額では納めすぎの場合には還付を申告できます。
税率の内訳
漫画家への報酬にかかる源泉徴収税率は100万円以下は10.21%、100万円を超える部分については20.42%です。これは、所得税10%(20%)に復興特別所得税0.21%(0.42%)を加えたものです。
たとえば100万円の報酬に対しては10万2,100円が源泉徴収され、差し引いた額が振り込まれます。報酬額が変わると徴収額も変わるため、簡単な税額シミュレーションを行うと安心です。
なお、投資型クラウンドファンディングでの源泉徴収税率は20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)となっているので注意しましょう。
確定申告で還付を受けるには
源泉徴収で引かれた税金が本来の納税額より多かった場合には確定申告をすればその差額が返ってきます。これが「還付」です。
確定申告の受付は通常2月中旬から3月15日までですが、還付申告は5年間さかのぼって可能です。確定申告書Bの「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄に記入して、必要書類を添えて還付を受けます。
還付請求の条件
還付を受けるには、源泉徴収された額が本来の納税額より多いことが必要です。たとえば、経費や控除の計上により課税所得が少なくなると、引かれ過ぎた分が返金されます。
また、確定申告することが必要です。過去5年までさかのぼって申告が可能なため、過去の支払調書を確認し、不足なく申告しましょう。
計算例
たとえば、報酬が100万円の場合、源泉徴収額は10.21%で10万2,100円です。経費や控除を申告した結果、最終的な納税額が8万円であれば、差額の約2万2,100円が還付されます。計算時は控除や特例を適用することで還付額が増える可能性もあるため、シミュレーションを行うと安心です。
還付金の受取まで
確定申告を提出してから還付金が口座に振り込まれるまでは、通常1~1か月半ほどかかります。申告書の内容や添付書類等の審査など、還付を適正に行うための期間と説明されています。自宅からe-Taxで申告すると3週間程度で還付が受けられます。税理士事務所に依頼する場合もe-Taxで申告を行うので、3週間程度で還付が可能です。
申告時にマイナンバーや銀行口座情報を正しく記載し、還付金が入金された際は税務署からの通知を確認しましょう。
見落としがちな節税ポイント3つ
確定申告では、経費計上や控除を適切に行うことで税負担を軽減できます。特に漫画家は画材や取材費用、作業スペースの家賃など、仕事に関わる多くの出費を経費にできます。
さらに青色申告特別控除を活用すれば、最大65万円の所得控除を受けることも可能です。ここでは、特に見落としがちな3つの節税ポイントを紹介します。
経費計上の必須項目
漫画制作に必要な画材費やデジタル機材、ソフト代はもちろん、取材にかかった交通費や書籍代も経費として計上可能です。領収書やレシートを整理し、仕事用と私用を明確に分けておくことが重要です。副業収入やプライベートの支出と混同しないよう、日頃から収支を記録しておくと、申告がスムーズです。
また、文房具、郵送費、印刷費、外注したアシスタントへの支払いも忘れずに経費として計上しましょう。外注費については、源泉徴収の対象になる場合があるため、支払い時に注意が必要です。会議費や打ち合わせの飲食代も、仕事に関連していれば経費対象となる場合があります。ただし、全額が経費になるわけではないので、用途の記録と領収書へのメモが重要です。経費性があいまいな支出は、税理士へ相談して判断を仰ぐのが安全です。
家事按分の活用
自宅を仕事場として利用している場合、家賃・光熱費・通信費の一部を経費に計上できます。計算は「使用面積」や「使用時間」に基づいて合理的に按分します。 根拠のない割合で計上すると否認されるリスクがあるため、面積や稼働時間をメモしておくことが大切です。電気代やインターネット代も対象にできるので、見逃さないようにしましょう。
たとえば、6畳の部屋のうち3畳分を仕事用スペースとして1日8時間使っているなら、その割合を算出して経費に計上できます。家賃10万円のうち、30%を業務に使っていれば3万円が経費対象になるという考え方です。
水道光熱費、Wi-Fi代、携帯料金なども合理的に按分すれば、毎月の負担軽減につながります。ただし、按分根拠が曖昧だと税務調査で否認されることがあるため、計算式や使用実態を記録に残しておくことが重要です。
青色申告特別控除
青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられます。また、赤字が出た年には「純損失の繰越控除」で翌年以降の黒字と相殺が可能です。
青色申告特別控除を利用するための条件は、複式簿記で帳簿をつけ、期限内に申告することです。複式簿記をつけるのに手間はかかりますが、税額軽減効果が大きく、長期的に活動を続ける漫画家には有効な制度です。
確定申告の手続きとスケジュール
確定申告には、e-Tax(電子申告)と窓口提出の2種類があります。e-Taxは自宅から24時間申告が可能で、押印が不要なためスピーディーです。一方、窓口申告は書類提出の安心感があります。
提出期限は毎年3月15日が基本で、期限を過ぎると加算税が発生する場合もあります。期限前にチェックリストを作成し、早めに準備することが大切です。
必要書類と提出方法
確定申告には確定申告書を作成し必要書類を添付して提出する必要があります。支払調書・青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)のほかにも、申告内容によって必要な書類があるので、注意しましょう。
紙で提出する場合は、書類を税務署へ持参または郵送し、本人確認書類や押印(必要な場合)も忘れずに準備しましょう。e-Taxで提出する場合は、事前にマイナンバーカードやICカードリーダー、またはマイナポータル連携の設定が必要です。
提出期限と延長申請
通常、確定申告の提出期限は毎年3月15日です。この日までに申告を終えないと、無申告加算税や延滞税が課されます。
ただし、災害や病気など特別な事情がある場合には、所轄税務署に「延長申請」をすることで期限の延長が認められるケースもあります。万一、期限を過ぎてしまった場合には、速やかに税務署に相談し、申告ししましょう。
e-Taxと窓口申告の違い
e-Taxは24時間申請が可能で、押印不要・還付処理が早いなど多くのメリットがあります。マイナンバーカードとスマホがあれば、初心者でも比較的簡単に申告できます。
一方、窓口申告は窓口で申告書をチェックしてもらえるというメリットがあり、手続きに不安がある方に向いています。ただし、税務署の混雑を避けるには予約が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
まとめ

漫画家にとって、源泉徴収は避けられない制度ですが、確定申告を正しく行えば税金が戻ってくる可能性があります。さらに、経費や青色申告特別控除、家事按分などの制度を活用すれば、税負担を大きく軽減することも可能です。
「何から始めていいかわからない」「計算が苦手」という方は、まずは田中貴久公認会計士事務所にお問い合わせください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。