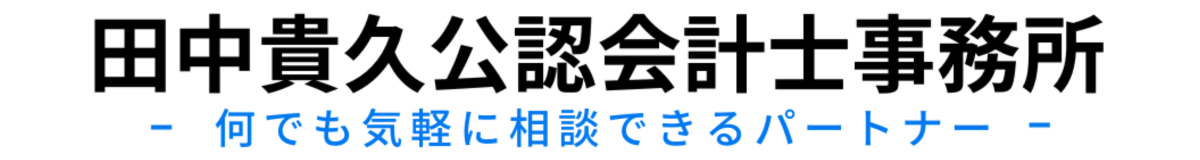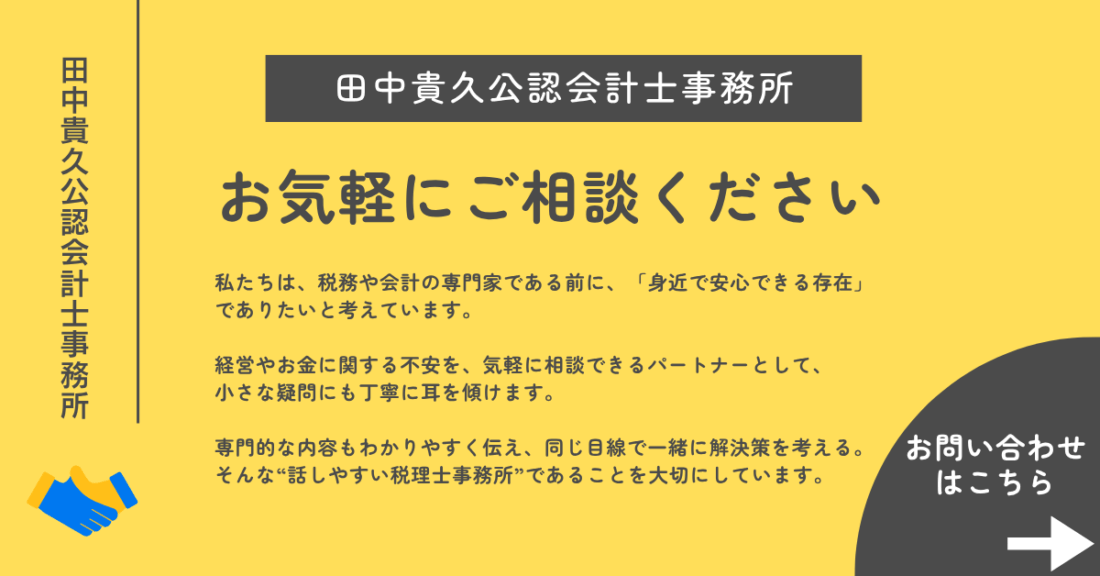イラストレーターとして活動を始めると、「どんな税金を払う必要があるの?」という不安を抱く人は多いでしょう。特にフリーランスや学生の場合、初めての確定申告や親の扶養との関係など、考えるべきことが多くなります。
本記事では、イラストレーターが知っておくべき代表的な税金の種類を整理し、学生やフリーランスとして活動する際の注意点をわかりやすく解説します。
イラストレーターに関わる4つの税金
イラストレーターが納める可能性のある税金には、大きく分けて「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4種類があります。どの税金がどんな性質を持ち、どのタイミングで支払いが発生するのかを理解する必要があります。
所得税は1年間の所得に応じて課税され、住民税は翌年にお住まいの自治体へ納めます。消費税は売上が1,000万円を超える規模になったときに発生し、個人事業税は事業の種類に応じて課される税金です。こうした全体像をつかんでおけば、「知らなかったせいで突然大きな負担が来た」という事態を防ぐことができます。
①所得税:1年間の「所得」にかかる税金
所得税は、イラストレーターが1年間に得た所得に応じて課される税金です。ここでいう「所得」とは売上から必要経費を差し引いた金額のこと。例えば、売上が100万円で経費が30万円なら、課税の対象となる所得は70万円です。所得税は累進課税方式を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がります。確定申告を通じて計算し、納税額が決まります。
収入が少ない段階でも、源泉徴収されている場合は注意が必要です。確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が「還付金」として戻ってくる可能性があります。
②住民税:お住まいの自治体に納める税金
住民税は、前年の所得をもとに翌年6月から1年間、住んでいる自治体に納める税金です。たとえ所得税が少額で済んでも、住民税は一律課税の部分があるため、注意が必要な税金です。
フリーランスのイラストレーターの場合、確定申告をすればそのデータが自治体に送られ、自動的に住民税が計算されます。アルバイト収入とイラストの収入を合わせた所得に基づいて課税されるため、「副業だから大丈夫」と考えるのは危険です。翌年にまとめて請求が来るため、日頃から住民税分を意識して資金を管理する必要があります。
③消費税:売上が1,000万円を超えたら
消費税は、売上が大きくなって初めて関係してくる税金です。原則として、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、顧客から預かった消費税を納めなければなりません。イラストレーターの場合、売上が急に増えた年の2年後に課税が始まるため、思わぬタイムラグがあります。
また、インボイス制度の導入により、売上が1,000万円以下でも取引先からインボイス登録を求められ、課税されるケースがあります。取引環境や将来の売上見込みを踏まえて、早めに制度を理解し、対応を検討することが大切です。
④個人事業税:特定の事業にかかる税金
個人事業税は、都道府県が課す税金で、対象となる事業を営む場合にかかります。イラストレーターは「デザイン業」として対象になるケースが多く、年間の事業所得が290万円を超えると課税されます。
税率は所得の5%程度で、事業が軌道に乗ってから発生する税金といえます。課税対象となるかどうかは事業内容や収入額によって変わるため、税務署や都道府県税事務所で確認しておくと安心です。
【学生向け】特に注意すべき扶養と税金の壁
学生としてイラストの仕事をする場合、自分の税金だけでなく「親の扶養」に影響する点も考慮する必要があります。扶養から外れると親の税額が増える可能性があるため、収入額の管理が重要です。特に「合計所得の壁」や「勤労学生控除」といった仕組みを理解しておけば、無用なトラブルを避けることができます。
合計所得58万円の壁:扶養から外れるライン
学生イラストレーター自身の合計所得が年間58万円を超えると、親の扶養から外れてしまいます。なお、給与所得のみである場合には123万円を超えた場合に扶養から外れます。扶養から外れると親の所得税や住民税が増えるだけでなく、社会保険の扶養条件にも影響が出る可能性があります。そのため、アルバイト収入とイラスト収入を合わせてどのくらいになるのかを常に意識することが大切です。
収入が増えること自体は悪いことではありませんが、扶養の枠を超えると家庭全体の税負担が増える点を理解しておきましょう。
勤労学生控除とは?
学生がイラストレーターとして収入を得る場合、「勤労学生控除」が適用できるかどうかが大切なポイントになります。勤労学生控除とは、一定の要件を満たす学生が働いて得た所得から、最大27万円を所得から差し引ける制度です。これにより、課税対象となる所得額が減り、税負担を軽くすることができます。
適用要件は主に4つです。
①勤労による給与所得や事業所得があること
②合計所得金額が85万円以下であること(給与所得控除後)
③そのほかの所得(仕送りや年金など)が10万円以下であること
④特定の学校の学生、生徒であること(学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など)
イラストレーターとしての報酬が事業所得や雑所得にあたり、加えてアルバイトの給与がある場合、収入合計が一定額を超えなければ控除を受けられる可能性があります。
この控除を活用すれば、学生時代から積極的に仕事をしても税負担が大きくならずに済みます。例えば、アルバイトとイラスト収入を合わせた所得が60万円であれば、勤労学生控除によって27万円が差し引かれ、実質的な課税対象は33万円に抑えられます。その結果、所得税や住民税の負担を軽減できるのです。親の扶養条件と併せて、勤労学生控除の適用を検討することは、学生イラストレーターにとって賢い税金対策といえます。
フリーランスイラストレーターと税金の付き合い方
フリーランスのイラストレーターにとって、税金の知識は単なる義務の理解にとどまらず、事業を守り育てるための重要なスキルです。税金を正しく理解し、計画的に対応できれば、資金繰りを安定させ、事業の成長に資金を回すことができます。一方で、知識が不足していると、納税額の見込み違いや経費計上の漏れにより、思わぬ負担を抱えるリスクがあります。
特にフリーランスは給与所得者と違い、自ら確定申告を行わなければならないため、税務管理が直接的に事業の健全性に影響します。
節税の基本は「正しい経費計上」から
フリーランスのイラストレーターにとって最も基本的かつ効果的な節税方法は、「正しい経費計上」です。経費とは、収入を得るために必要な支出を指し、事業に関連する出費であれば幅広く認められます。例えば、パソコンやタブレットなどの機材費、ペンや紙などの画材費、ソフトウェアの利用料、打ち合わせにかかる交通費や通信費などは代表的な経費です。
経費を正しく計上すれば、所得を圧縮でき、その分課税される金額も減ります。例えば売上300万円で経費が100万円なら、課税対象は200万円です。経費を漏れなく計上していれば、余計な税金を支払わずに済むわけです。
逆に経費を記録していなければ、結果的に利益が多いとみなされ、税金が増えてしまいます。領収書や請求書は必ず保存し、クラウド会計ソフトなどを活用して日々の経費を整理することが重要です。
税金の悩みは、専門の税理士に相談しよう
フリーランスのイラストレーターは、案件ごとに契約内容や収入形態が異なることが多く、税務処理も複雑になりがちです。
例えば、国内クライアントと海外クライアントでは源泉徴収の有無が異なったり、報酬の支払い方法によって計上時期が変わったりします。こうした多様な状況に一人で対応するのは容易ではありません。
そこで頼りになるのが税理士です。税理士に相談すれば、最新の税制に基づいた適切なアドバイスが受けられるほか、節税の工夫や資金繰りの改善方法など、実務に即した助言を得られます。また、確定申告書や各種申請書類の作成を代行してもらえるため、手間や不安を大幅に減らすことが可能です。
イラストレーターのようなクリエイティブ職の特性にも理解がある税理士であれば、仕事の実態に沿ったアドバイスが受けられます。フリーランスとして長く安定して活動していくためには、専門家の力を借りることも積極的に検討すべきでしょう。
まとめ

イラストレーターとして活動を始めると、想像以上に多様な税金が関わってきます。代表的なものは「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4種類であり、それぞれ課税の仕組みやタイミングが異なります。特に、売上や所得の規模によって負担が大きく変わるため、早めに全体像を理解しておくことが大切です。
学生のイラストレーターは、自分の税金だけでなく「親の扶養」との関係にも注意する必要があります。扶養から外れるラインである合計所得58万円(給与のみなら123万円)の壁や、条件を満たせば税負担を軽減できる「勤労学生控除」などを理解しておくと安心です。家庭全体の税金や社会保険料に影響するため、収入額を常に意識して活動しましょう。
一方、フリーランスとして本格的に活動するイラストレーターにとっては、税務知識は事業を支える大切なスキルです。節税の基本は「正しい経費計上」であり、日々の出費を整理・記録することが将来の大きな差につながります。さらに、制度や契約形態が複雑になりやすいため、不安があれば早めに税理士に相談することが有効です。専門家の助言を受けることで、適切な節税対策や資金繰りの改善ができ、安心して創作活動に集中できます。
つまり、イラストレーターにとって税金は避けて通れないテーマですが、正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りれば決して怖いものではありません。早い段階で知識を整理し、自分に合った対応をとることで、創作と事業の両立を安定させることができるでしょう。
所得税など税金にについて不安がある場合には、イラストレーターの税金を数多くサポートしている田中貴久公認会計士事務所にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。