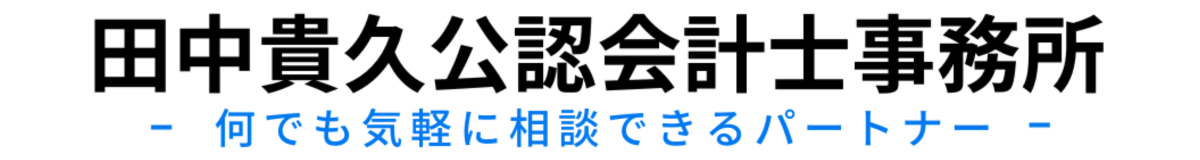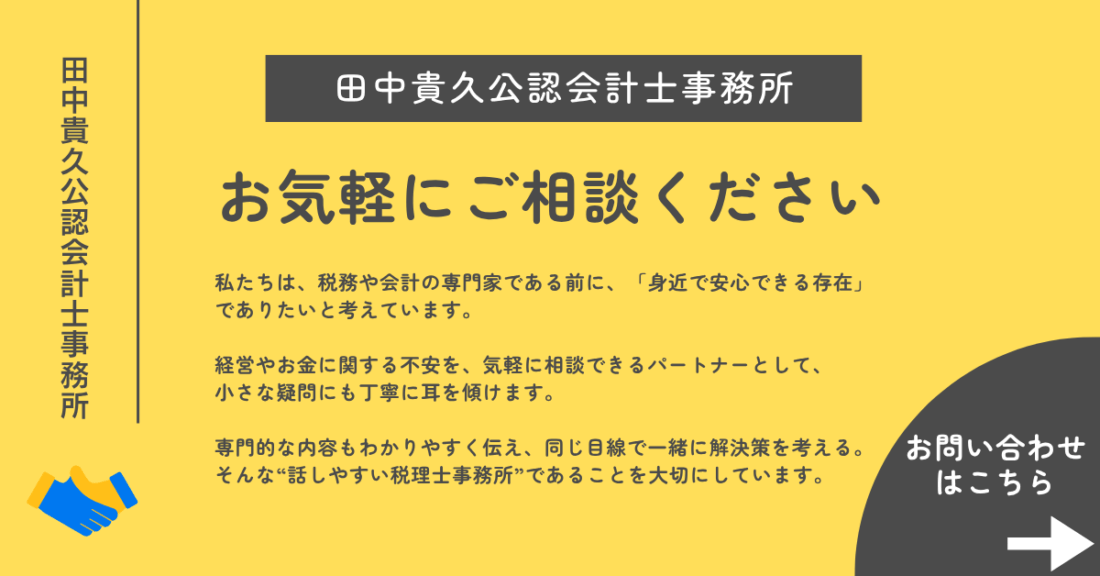YouTubeで収益化に成功すると、次に直面するのが「税金はどうなるのか?」という不安です。広告収入や案件報酬が増えると、所得税・住民税・消費税・個人事業税といった税金が関わってきます。
本記事では、YouTuberの税金の仕組みを解説し、収入ステージ別の負担額や具体的な節税方法、そして万一払えない場合の対処法について解説します。
YouTuberが支払う4つの税金とは?
YouTuberとして活動する人が支払う可能性がある税金には、主に「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4種類があります。
所得税:1年間の「所得(収入-経費)」に対して課される税金です。累進課税方式を採用しており、所得が増えるほど税率も上がります。確定申告によって計算され、原則として翌年3月15日までに納める必要があります。
住民税:前年の所得を基に翌年に支払う地方税です。所得に応じた「所得割」と、所得に関係なく一律にかかる「均等割」があり、思ったより負担が重く感じられるケースも少なくありません。
消費税:前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、顧客から預かった消費税を納める必要があります。インボイス制度によって、売上が1,000万円以下でも登録を求められる場合がある点にも注意が必要です。
個人事業税:デザイン業など特定の事業を営む場合に課される税金です。イラストレーターや動画クリエイターは対象となりやすく、年間事業所得が290万円を超えると課税されます。
収入が増え始めた段階で、どの税金が関わってくるのかを押さえておくことが重要です。
【収入ステージ別】税金はいくらになる?シミュレーション
YouTuberの税金負担は、収入が増えるごとに大きくなります。ここでは所得額に応じて「副業YouTuber」「専業YouTuber」「人気YouTuber」という3つのステージに分け、それぞれでどのように税金がかかるのかを解説します。
副業レベルでは所得20万円超から申告が必要になり、専業では所得税率の上昇や住民税負担が重くのしかかります。さらに人気YouTuberとなり所得800万円を超えると、消費税や個人事業税の影響も加わり、総合的な税負担が大きくなります。
副業YouTuber(所得20万円~300万円)
会社員やアルバイトとして給与を得ながら、副業としてYouTubeを運営しているケースでは、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。ここでいう所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。たとえば広告収入が40万円あり、機材費やソフト代など経費が15万円かかった場合、所得は25万円。基準の20万円を超えるため、申告が必要です。
この段階では所得税率は5%~10%程度で済むケースが多いですが、住民税(約10%)も加わるため、実際の負担感はそれ以上です。また、副業が会社に知られるのを避けたい場合には「住民税の普通徴収」を選ぶことが重要です。給与からの天引き(特別徴収)のままだと副業収入が勤務先に通知されるリスクがあるため注意しましょう。副業YouTuberにとっては、申告の有無だけでなく「副業バレ防止の工夫」も実務的に大切なポイントです。
専業YouTuber(所得300万円~800万円)
専業でYouTubeを生業にしている場合、所得が300万円を超えるあたりから税金負担が一気に重くなります。所得税率は10%から20%に上がり、住民税も含めると実質的な税率は20~30%程度に達します。たとえば所得が500万円であれば、概算で100万円前後を税金として納める必要があるイメージです。
さらにこの段階では、個人事業税が課される可能性もあります。動画制作は「デザイン業」とみなされるケースが多く、年間所得が290万円を超えると課税対象になります。税率は5%前後で、他の税金と合わせるとかなりのインパクトです。
専業YouTuberは、収入が増えると同時に経費の範囲も広がります。機材のアップグレード、外注の活用、企画に伴う交通費や取材費などを正しく経費計上すれば、課税所得を抑えることが可能です。税金対策を怠ると大きな負担に直結するため、早めに帳簿付けや青色申告に取り組むことが不可欠です。
人気YouTuber(所得800万円~)
人気YouTuberの段階に達し、所得が800万円を超えると、税率はさらに高くなります。所得税は23%から33%、住民税も合わせると実質30~40%程度の税率になることも珍しくありません。所得1,000万円を超えると累進課税の影響で手元に残る割合は大幅に減り、「思ったより税金で持っていかれる」という声が多いのもこの層です。
加えて、この段階では消費税の納税義務が発生します。前々年の売上が1,000万円を超えると免税事業者ではいられず、顧客から預かった消費税を納めなければなりません。さらにインボイス制度の導入によって、免税事業者のままでは取引先から敬遠されるリスクも高まっています。
人気YouTuberほど「節税」と「資金管理」が死活問題になります。法人化によって税率を抑えたり、家族を役員にして報酬を分散させたりといった戦略的な対策も必要です。大規模な収入を得るからこそ、専門家の力を借りて長期的な視点で税務戦略を立てることが重要です。
YouTuberの最強の節税テクニック
YouTuberにとって、収入が増えれば増えるほど「いかに節税するか」が重要になります。ここでは代表的な節税テクニックを紹介します。
まず基本は、青色申告を選択することです。開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、65万円(または55万円)の青色申告特別控除を受けられます。帳簿付けは必要ですが、これだけで大幅に課税所得を減らせるため効果は絶大です。さらに、赤字を翌年以降3年間繰り越せる「損失の繰越控除」や、家族に仕事を手伝ってもらった場合に給与を経費にできる「青色事業専従者給与」なども使えます。
次に、正しく経費を計上すること。撮影用のカメラやマイク、編集用PCやソフト、動画企画で使った衣装や小道具、ロケでの交通費や宿泊費など、動画制作に関わる支出は原則として経費にできます。自宅兼スタジオの場合は、家賃や光熱費の一部を事業割合に応じて按分して経費にできるのも大きなポイントです。
さらに、節税の大きな分岐点となるのが法人化です。個人事業主の場合、所得が増えるほど税率も上がる累進課税ですが、法人化すれば税率は一定に抑えられます。たとえば、利益が800万円を超えると法人税の方が有利になるケースも少なくありません。また、法人化すれば交際費や役員報酬といった経費の幅が広がり、社会的な信用度も高まります。
最後に、小規模企業共済やiDeCoの活用もおすすめです。小規模企業共済は掛金が全額所得控除となり、将来の退職金代わりにもなります。iDeCoも同様に掛金が所得控除対象ですので、節税と資産形成を同時に実現できます。
節税は単発のテクニックではなく、会計管理と将来を見据えた戦略の積み重ねです。規模が大きくなるほど専門的な判断が必要になるため、早い段階で税理士に相談するのが最も効果的な節税策といえます。
【トラブル】税金が払えないとどうなる?
YouTuberとして収入が急増したときに多いトラブルが、「想定以上に税金が発生し、払えなくなる」というケースです。では、実際に納税ができなかった場合はどうなるのでしょうか。
まず、延滞税や加算税が発生します。納期限までに税金を納めないと、未納額に対して延滞税が日割りで加算されます。さらに、期限までに申告をしていない場合には無申告加算税、過少に申告していた場合には過少申告加算税が課される可能性があります。これらは本来の税額に上乗せされるため、負担が一層重くなります。
さらに、督促や差し押さえのリスクもあります。納税を長期間滞納すると、税務署や自治体から督促状が届き、それでも支払わない場合は銀行口座や給与、売上入金口座などが差し押さえられることもあります。YouTuberにとっては、活動資金が差し押さえられると継続的な動画制作にも支障が出てしまいます。
「払えないから後回しに…」という対応は危険であり、税金滞納は最も避けるべきリスクのひとつです。実際には、分割納付や納税猶予といった救済制度も用意されているため、払えない場合には必ず早めに税務署に相談することが重要です。
【解決策】税金が払えないときの相談先
税金が払えない状況に陥った場合、どこに相談すればよいのでしょうか。最初に頼るべきは税務署です。納税者の状況に応じて、分割納付や猶予制度の案内をしてもらえます。たとえば「換価の猶予」という制度では、1年間差し押さえられ売却される換価を免れることができます。
次に、税理士への相談も効果的です。税理士は、現状の収入・支出を見直し、分割納付のプラン作成や資金繰り改善のアドバイスをしてくれます。特にYouTuberの場合は収入の増減が激しく、翌年以降の税負担見込みを踏まえて計画を立てることが重要です。専門家と一緒に対策を練ることで、税金が払えない事態の将来の再発防止にもつながります。
まとめ

YouTuberの税金は、収入の規模によって大きく変化します。節税の基本は青色申告と経費計上であり、さらに規模が大きくなれば法人化や共済制度の活用も視野に入れるべきです。逆に、納税を後回しにすると延滞税や差し押さえといったリスクに直結します。もし払えない状況に陥っても、税務署や税理士に相談しましょう。
田中貴久公認会計士事務所はYouTuberの税務に通じており、申告や節税についてのアドバイス経験が豊富なので、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。