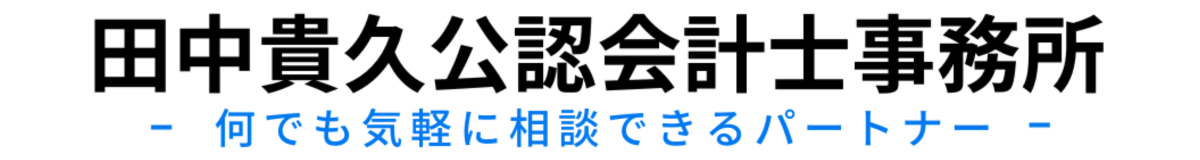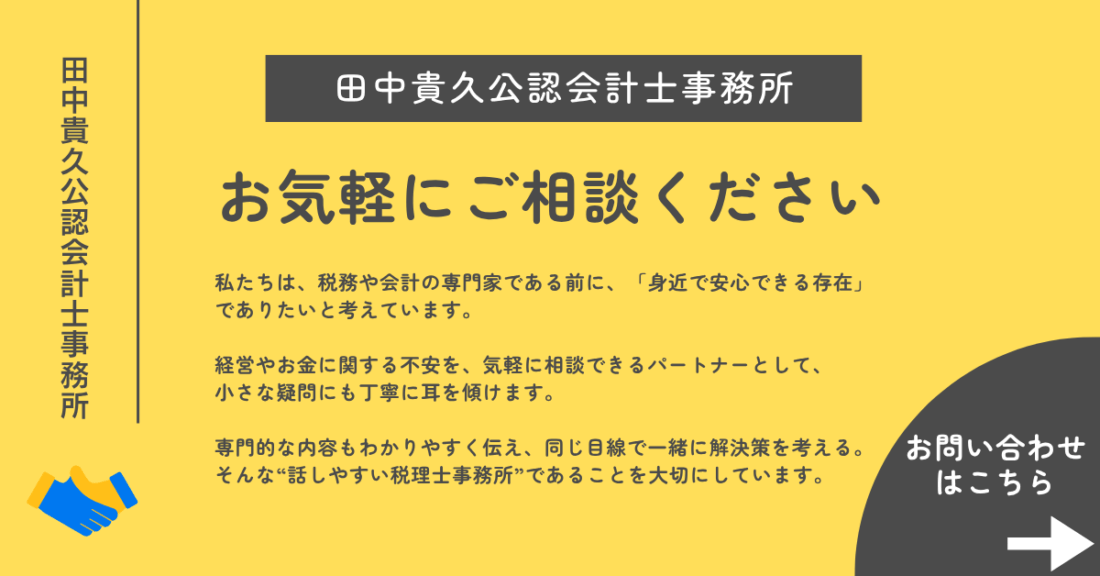スキルや知識をオンラインで売買でき、クリエイターの収入源として人気のココナラ。利用している方の中には「確定申告は必要なの?」「源泉徴収ってどう処理すればいいの?」と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、ココナラ特有の源泉徴収の仕組みや、確定申告が必要になるケースを本業・副業に分けてわかりやすく解説します。
ココナラの「源泉徴収あり/なし」の仕組み
ココナラの収入を確定申告するうえで重要なのが「源泉徴収があるかどうか」です。購入者やサービスの種類によって源泉徴収される場合とされない場合があり、処理方法が異なります。まずはその仕組みを理解しましょう。
源泉徴収されるのはどんな時?
ココナラでは、すべての取引が源泉徴収の対象になるわけではありません。源泉徴収されるのは、購入者が法人・個人事業主であり、かつサービス内容が「デザイン」「ライティング」「音楽制作」など、税法上の源泉徴収区分に該当する場合に限られます。
たとえば、法人が依頼したロゴ制作や記事作成の報酬は源泉徴収の対象です。一方で、個人同士の取引や、源泉徴収区分外のサービス(占い・相談など)は対象外です。
源泉徴収の対象となるかどうかは、依頼を受けた購入者属性やカテゴリに左右されるため、自分の取引内容を確認することが大切です。
源泉徴収がある場合、ココナラの売上明細に「源泉徴収税額」が表示されるので、後の確定申告の際にはその金額を正しく反映させましょう。
源泉徴収された税金はどうなる?(確定申告で還付の可能性)
源泉徴収は「税金の前払い」にすぎません。取引時に差し引かれた税金は、確定申告を通じて1年間の収入と経費を集計し、正しい所得税額を計算し直します。
たとえば、ココナラで30万円の売上があり、そのうち法人案件で3万円分の源泉徴収がされたとします。経費を差し引いた実際の課税所得が少なければ、結果的に税金を払いすぎていたことになり、還付される可能性があります。逆に、他の収入と合算して税額が不足している場合は追加納付が必要です。
ココナラの収入、確定申告はいくらから必要?
ココナラでの収入が確定申告の対象になるかどうかは、「副業」か「専業」かによって条件が異なります。副業で活動している会社員や学生と、専業の個人事業主では、確定申告のボーダーラインが違うため注意が必要です。
ここでは、それぞれの立場による確定申告が必要となる基準を解説します。
会社員・学生など(副業)の場合:所得20万円の壁
会社員や学生が副業としてココナラを利用している場合、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
ここでいう「所得」とは、売上から経費を差し引いた金額のことを指します。たとえば、年間で40万円の売上があり、経費が25万円かかった場合、所得は15万円となり、20万円以下なので申告義務はありません。しかし、所得が21万円であれば確定申告の対象になります。
この「20万円の壁」は、副業をしている場合の所得税に関するものです。そのため、住民税はこの特例が適用されません。そのため、所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要となります。
副業の収入を隠してしまうと、勤務先に住民税額の変化から発覚する可能性もあるため、正しく申告することが重要です。
専業(個人事業主)の場合:所得95万円の壁
専業でココナラを利用し、個人事業主として活動している場合は、年間の所得が基礎控除額である95万円を超えると確定申告が必要になります。
古い情報では48万円という記載がありますが、これは令和6年までのものなので注意しましょう。
令和7年からは、基礎控除額は所得に応じて段階的となります。所得が132万円以下である場合には基礎控除額が95万円となるため、所得が95万円以上となると確定申告が必要です。
たとえば、ココナラでの売上が100万円あり、経費が10万円かかった場合、所得は90万円となり基礎控除の範囲内です。この場合は申告義務はありません。
もっとも、青色申告を利用して節税したい場合や、他の収入との兼ね合いによっては申告した方が有利になることもあります。
専業の場合は、副業と異なり「20万円の壁」は適用されません。基礎控除の95万円を超えるかどうかが明確な判断基準になるため、年間の収支をきちんと記録して、早めに確認しておくことが大切です。
【やり方】ココナラの確定申告、具体的な手順
ココナラでの収入を正しく申告するには、売上や源泉徴収の有無を把握したうえで、確定申告の手順に沿って準備を進める必要があります。以下の流れを押さえておけば、申告はスムーズに行えます。
・年間の売上・経費を集計する
まずはココナラの「売上明細」から、年間の売上金額と源泉徴収された税額を確認します。そのうえで、必要経費(通信費・ソフト代・資料購入費など)を整理して、所得額(売上-経費)を計算しましょう。
・源泉徴収票や支払調書を確認する
法人からの取引がある場合、源泉徴収された金額がココナラの明細に記録されています。確定申告ではこの金額を反映させることで、払いすぎた税金があれば還付を受けられます。ココナラには支払調書の発行の制度がなく、発行は法的義務ではないので、もらえない可能性が高いので、源泉徴収票をしっかり管理するようにしましょう。
・申告方法を選ぶ(白色申告か青色申告か)
専業で継続的に活動するなら、節税メリットの大きい青色申告がおすすめです。青色申告を選ぶと65万円の控除や赤字の繰越が可能になるため、収入が安定していなくても将来的に有利です。副業であっても、事業性があれば青色申告ができます。
・確定申告書を作成する
確定申告書を作成します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やfreee、マネーフォワードなどの会計ソフトを利用すれば、ココナラの売上データを反映させて簡単に計算できます。売上・経費・源泉徴収額を入力するだけで、自動的に税額が算出されます。
・確定申告書を提出する
作成した確定申告書を提出します。e-Taxを利用すれば自宅から申告が完了します。マイナンバーカードやICカードリーダー、スマートフォンでの読み取り機能を使えば手続きがスムーズです。紙で提出する場合は、税務署に郵送または持参しましょう。
・納税または還付を受ける
申告の結果、納める税額がある場合は期限までに納税します。払いすぎがあれば還付申告となり、登録した口座に振り込まれます。還付金は数週間から1~2か月で入金されるのが一般的です。
確定申告しないとバレる?無申告のリスク
「ココナラでの収入は少額だから、確定申告をしなくてもバレないのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、実際には無申告が税務署に発覚します。
ココナラの取引はインターネット上で行われ、売上や源泉徴収の情報はプラットフォームに記録されます。そのため、税務署が把握できる状態にあるのです。
もし申告を怠ると、以下のようなリスクが生じます。
・延滞税・加算税が課される
本来納めるべき税金を期限までに申告・納付しなかった場合、延滞税や無申告加算税が加算されます。とくに意図的な隠蔽が疑われた場合には、重加算税が課されることもあります。
・住民税から勤務先にバレる可能性
副業の場合、住民税の額が変わることで勤務先に収入の存在が発覚するケースがあります。確定申告を行わないと、会社に説明がつかず、思わぬトラブルを招く恐れがあります。
・税務調査の対象となるリスク
無申告が続くと、税務署から調査を受けることもあります。過去数年分をさかのぼって指摘され、まとめて追徴課税を受ける可能性も否定できません。
確定申告の代行など、税理士に相談するメリット
ココナラでの収入は、源泉徴収の有無や副業・専業の違いによって確定申告のルールが複雑になりがちです。
売上明細や経費を整理し、自分で申告することも可能ですが、間違った処理をしてしまうと余分な税金を払ったり、逆に申告漏れでペナルティを受けたりするリスクがあります。そこで有効なのが、税理士への相談や申告代行サービスの利用です。
税理士に相談することで得られる主なメリットは以下のとおりです。
・複雑な計算を正確に処理できる
・時間と労力を大幅に削減できる
・税務調査やトラブルへの備えになる
メリット1:複雑な計算を正確に処理できる
源泉徴収の反映や、経費の仕分け、青色申告の特典適用など、専門的な部分を正確に処理してもらえます。とくに青色申告を検討している人にとっては、節税効果を最大化するための強い味方になります。
メリット2:時間と労力を大幅に削減できる
確定申告は慣れていないと数日以上かかることもありますが、税理士に依頼すれば本業やココナラでの活動に集中できます。
メリット3:税務調査やトラブルへの備えになる
税理士が申告内容をサポートしていれば、税務署からの問い合わせにも安心して対応できます。無申告や誤申告による追徴課税のリスクを減らせるのも大きなメリットです。
とくにココナラを副業から専業に広げていきたい方や、売上が増えて申告内容が複雑になってきた方は、税理士に相談する価値が高いでしょう。費用はかかりますが、それ以上に節税やリスク回避の効果を得られる可能性があります。
まとめ

ココナラでの活動は、ちょっとした副業から本格的な事業まで幅広く展開できます。しかし、収入が発生する以上、正しい確定申告を行うことは避けられません。源泉徴収の有無や、所得20万円・95万円といった基準を正しく理解すれば、申告の必要性を判断しやすくなります。
無申告にすると、延滞税や加算税のリスク、住民税から勤務先に知られてしまうリスクなど、大きな不利益につながりかねません。一方で適切に申告をすれば、必要な物品を経費化できたり、還付を受けたりすることも可能です。
確定申告や所得税に不安があるのであれば、税理士に早めに相談することをおすすめします。
田中貴久公認会計士事務所はクリエイターの税務に通じており、経費化や確定申告についての実績豊富なので、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。