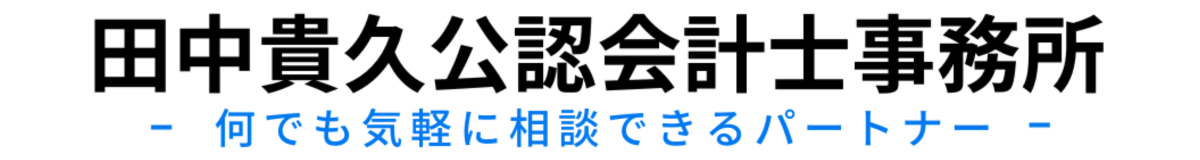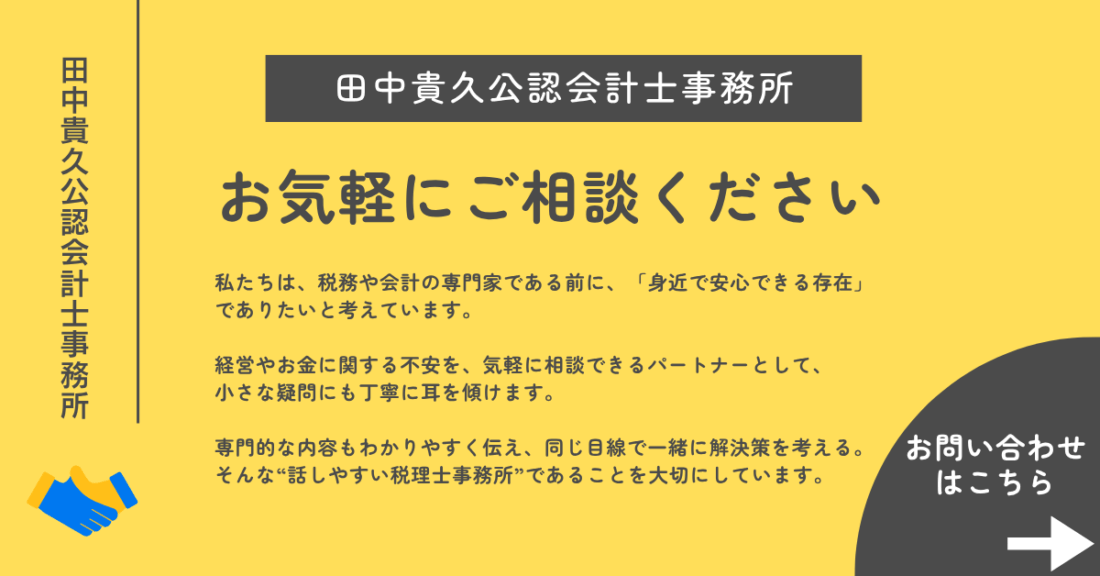ファンティアで収入を得始めると「確定申告はどうすればいいんだろう?」という悩みがでてくるでしょう。
この記事では、ファンティアで活動するクリエイターに向けて、確定申告が必要になる金額の基準と、具体的なやり方を分かりやすく解説します。
ファンティアの収入、確定申告が必要になるのはいくらから?
ファンティアの収入で確定申告が必要になるかは、ファンティアを含めたすべての合計所得が一定額を超えているかで決まります。所得とは収入から、その収入を得るためにかかった必要経費を引いた残りの額です。
いくら所得があると確定申告が必要になるのかは、専業でクリエイターをしているのか、それとも会社員やアルバイト・パートで給与をもらっているかで変わります。
それぞれの場合にわけて解説します。
専業の場合(所得95万円)
専業の場合は、ファンティア等を含む年間の課税所得(= 所得 − 各種所得控除)が生じたら確定申告が必要です。2025年分以降の基礎控除は「58〜95万円」(合計所得金額に応じて逓減)で、多くの方は95万円ですが一律ではありません。
副業の場合(所得20万円)
会社員やアルバイト・パートで給与をもらっており、年末調整がされている場合、ファンティアからの所得は副業扱いになります。
副業の場合、ファンティアを含めた給与以外の年間所得が20万円を超えていると確定申告が必要になります。
【売上】ファンティア収入の計上方法
確定申告における収入の計上タイミングは、入金があった時ではなく、原則として売上が発生した時です。
ファンティアでは当月の売上は翌月10日に集計され、翌月10日から翌月25日までに振込申請が行われた売上は翌々月10日に振り込まれます。例をあげると、3月の売上は4月10日に集計されるということです。
しかしこの場合、実際に売上が発生したタイミングで計上するのが原則のため、4月10日に集計された売上は、3月分の売上として計上します。
特に注意しないといけないのが12月の売上で、これは翌年の1月10日に集計されますが、12月分の売上のため今年の確定申告に含める必要があります。そのため、1月10日の集計を待たないと、確定申告に必要な売上がそろいません。
また、ファンティアは会員費・商品販売代金から手数料を引かれますが、売上に計上するのは手数料を引かれる前の金額です。
手数料は「支払手数料」勘定で経費に計上します。
なお、ファンからのチップやバックナンバーの売上も確定申告で計上しないといけない点にも注意しましょう。
ファンティア活動の経費にできるもの
ファンティアでの活動に直接関連する支出は経費に計上でき、経費計上分だけ所得が減るため、税金が抑えられます。
注意点として、あくまでファンティアでの活動に関連する支出のみが経費になります。プライベートでの使用目的で購入した本や飲食代は経費にできないため注意してください。
経費にできるものとしては、たとえば下記があげられます。
・同人誌の印刷費やグッズの材料費
・作業で使用するソフトやパソコンの購入費
・ロケ撮影で発生した旅費交通費
・撮影機材
・動画編集やサムネイル作成など一部の作業を外注した場合の外注費
・確定申告を依頼した場合の税理士費用
・事務所家賃や事務所の水道光熱費
また、自宅で作業している場合には、自宅の家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。ただし、プライベートと作業での使用が混在していますから、使用時間や作業スペースの面積などを基準とした合理的な基準で按分する必要があります。
たとえば、家賃9万円で自宅面積の1/3を作業スペースとしており、面積で家賃を按分する場合、経費計上できるのは3万円までとなります。
【やり方】ファンティアの確定申告、5つのステップ
ファンティアの確定申告について具体的なやり方を、5つのステップにわけて解説します。
ステップ①:青色申告か白色申告かを決める
ファンティアからの所得が「事業所得」に該当する場合、青色申告の方が有利です。青色申告では最大65万円まで事業所得から控除でき、その分、税額が抑えられます。
青色申告で確定申告したい場合は、青色申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。その年の1月16日以降に開業した場合は、開業した日から2か月以内に申請書を提出しなければなりません。
事前に「開業届」を税務署へ提出する必要があるため、また開業届を提出していない人は、提出するタイミングで青色申告承認申請書を一緒に提出するとよいでしょう。
ただし、ファンティアからの所得が事業所得と認められるにはいくつか条件があり、基本的な条件としてファンティアからの売上・経費を記帳し、帳簿の保存をする必要があります。
他の条件として、ファンティアからの収入が300万円以下で、副業としてファンティアでの活動をしている場合、給与所得に対する割合が10%を超えていなければ事業所得ではなく「雑所得」となる可能性があります。
また、ファンティアからの所得が例年赤字で、かつ赤字解消のための取り組みを実施していないとされると、雑所得とみなされる場合があるでしょう。
雑所得とされた場合は、青色申告の控除は受けられません。
ステップ②:収入と経費をまとめる
年間のファンティアからの収入と経費をまとめます。ファンティアでは12月分の売上は翌年1月10日に集計されるため、忘れずに売上に含めてください。
経費に関しては、実際に経費が発生していることを証明するために、計上する経費のレシートや領収書、請求書などを必ず取得して保管しておきましょう。
もし後になって税務調査が入った際はレシートや帳簿などの提出が求められることがあるため、すぐに提出できる状態にしておく必要があります。保管期間は5~7年間のため、7年間は保管してください。
また、本業で会社員やアルバイト・パートをしており給与収入がある場合、本業から受け取った「源泉徴収票」を保管しておき、源泉徴収票に記載されている給与所得や源泉所得税額を確定申告書に反映させます。
ステップ③:確定申告書を作成する
集計した収入や経費の額をもとに、確定申告書を作成します。
確定申告書を手書きで作成する方法もありますが、慣れていないとどこに何を書けばいいかわからず、間違えやすいです。
そのため、国税庁のWEBサイトから「確定申告書等作成コーナー」を利用するか、市販の確定申告ソフトを使うのをおすすめします。どちらも必要事項を記入するだけで確定申告書を作成できるので便利です。
ファンティアからの所得を事業所得にする場合は、白色申告では「収支内訳書」、青色申告では「青色申告決算書」を併せて作成する必要があります。
青色申告ではない申告は白色申告となり、白色申告の場合は事前の届け出は必要ありません。
青色申告の控除額は、簡易簿記で記帳した場合は10万円の控除、複式簿記で記帳した場合は55万円の控除、複式簿記かつe-Taxで申告した場合は65万円の控除になるため、いくら控除を受けたいかで記帳方法が変わります。
複式簿記は複雑なため税理士に依頼するか、自力で記帳する場合は確定申告までできる会計ソフトを使用するのをおすすめします。
ステップ④:使える控除をチェックする
確定申告では、所得から控除できる「所得控除」が複数あります。
たとえば、所得2,500万円以下であれば誰でも受けられる「基礎控除」、配偶者や扶養している家族がいる場合の「配偶者控除」や「扶養控除」、生命保険料を支払っている場合に一部を控除できる「生命保険料控除」などがあります。
これらの控除を受けるためには確定申告書に記載し、生命保険料控除など一部の控除では「控除証明書」が必要になります。
また、税額から直接控除できる「税額控除」もあります。
ステップ⑤:申告と納税を行う
確定申告の期限は原則として翌年の3月15日までのため、この日までに申告と納税を行う必要があります。
申告書の提出には、税務署の窓口に持参する方法、郵送する方法、ネットを使ってe-Taxで申告する方法の3つがあります。
税務署の窓口に持参する方法では、その場で間違いを指摘してくれる場合があるものの、確定申告時期になると大変込み合うため他の方法にした方が無難です。
郵送による方法の場合は本人確認書類や控除証明書などを添付する必要がありますが、e-Taxの場合はそういった書類を添付する必要はなく書類の保管だけでよいため、e-Taxによる方法をおすすめします。
e-TaxはWEB版とソフトウェア版の2つがあり、WEB版はスマホからでも申告可能です。画面の指示に従って入力すれば申告が完了します。
e-Taxを利用するにはマイナンバーカードを利用する「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法があります。ID・パスワード方式はあくまでマイナンバーカードを持っていない人のための暫定的な処置であり、いつまで利用できるかわからないため、可能であればマイナンバー方式にしましょう。
マイナンバー方式ではマイナンバーカードと、それを読み込むためのICカードリーダライタを用意する必要があります。
まとめ

ファンティアからの所得が一定額を超えた場合、確定申告が必要です。
確定申告は自分で行うこともできますが、やり方や経費計上の判断などに不安があれば、1人で悩まずに専門家である税理士に相談しましょう。
税理士に依頼することで確定申告の悩みが解消され、安心して創作活動を続けられます。
当事務所は、クリエイターへの豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。