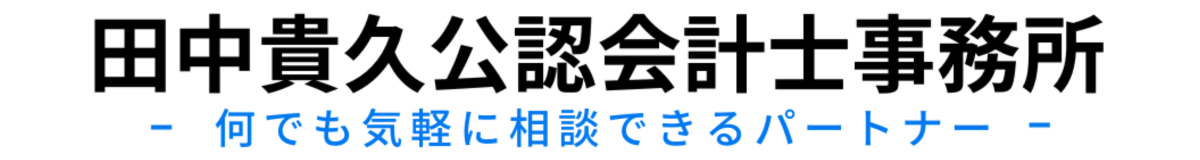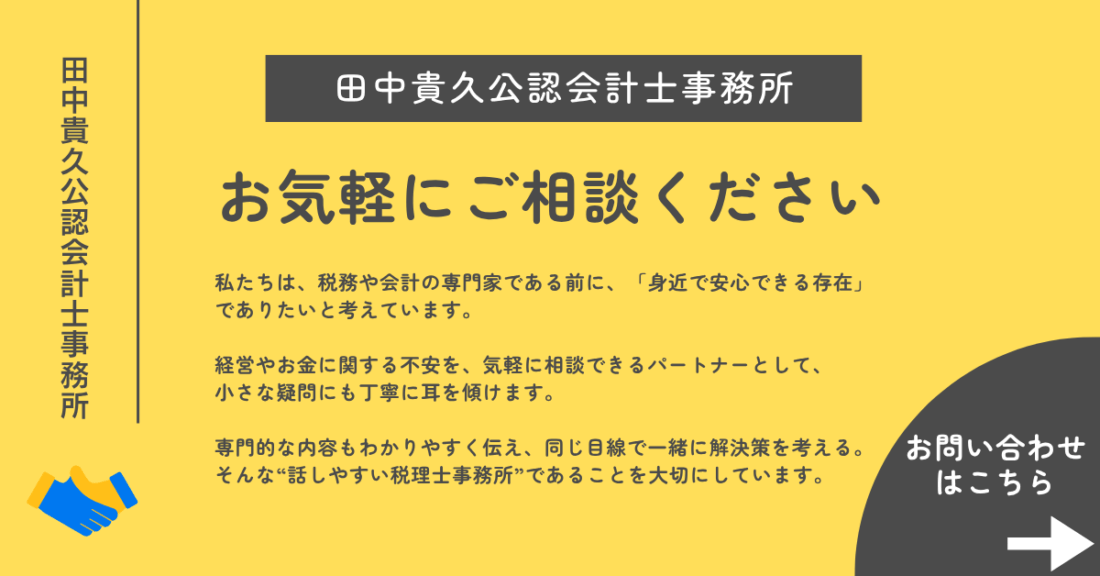クリエイターとして活動を続けていると、作品の評価や依頼の増加とともに収入が増えていきます。すると、これまであまり意識していなかった税金や確定申告に対して、不安を抱く方も少なくありません。
「自分でやるのは大変そう」「そろそろ税理士に頼むべきだろうか」と迷う方も多いでしょう。
そこで、本記事では、クリエイターが税理士に相談するメリットや、選び方の具体的なポイントを解説します。
クリエイターが税理士に相談する3つのメリット
税理士に依頼することは単なる「事務作業の代行」ではありません。確定申告の負担軽減だけでなく、節税の工夫や税務調査リスクの軽減といった幅広いメリットがあります。
ここでは、特にクリエイターにとって大きな3つの利点を紹介します。
確定申告や経理の手間から解放される
創作活動に専念したいクリエイターにとって、日々の帳簿付けや領収書整理は大きな負担です。さらに、会計や税務は頻繁に改正されるため、きちんと把握する必要があります。
税理士に依頼すれば、記帳から申告書の作成・提出まで一貫して任せることができます。これにより、膨大な時間を節約できるだけでなく、会計や税務の知識不足による誤りを防ぐことも可能です。専門家が正確に処理してくれるため、余計な税負担や修正申告のリスクも避けられます。
こうして浮いた時間を本業である創作活動やスキルアップに充てることができ、結果的に収益の拡大につながる点も見逃せません。
最適な節税アドバイスが受けられる
税理士は、クリエイター業特有の経費の扱いに精通しています。たとえば、イラスト制作ソフトの利用料、資料として購入した書籍や映像、さらには取材のための交通費など、正しく経費計上できるかどうか判断に迷う支出は多いものです。
税理士に相談すれば、これらを最大限に活用しつつ適法な節税策を提案してもらえます。さらに、青色申告の控除を活かした節税や、事業規模に応じた最適な会計処理方法など、専門的なアドバイスを受けることで税負担を軽減できるのです。
自分だけでは気づけない節税のチャンスを見逃さないためにも、税理士の存在は大きな助けになります。
税務調査のリスク軽減ができる
税務調査は、申告内容に不備や疑念があると実施されるため、独学での申告には不安を伴います。
特に、売上が増えたことで消費税の課税事業者になるタイミング(原則として、2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合)など、重要なポイントを見落とすと、後から税務調査のうえで追徴課税を受ける可能性があります。
税理士に依頼していれば、法令に基づいた正確な処理が行われるため、税務調査の対象となるリスクを大幅に減らせます。また、万が一調査を受けることになっても、税理士が代理人として対応してくれるため、精神的な負担も軽くなります。安心して創作活動を続けるためのリスク管理としても、税理士への相談は有効です。
クリエイター専門税理士を見つける4つのポイント
税理士と一口にいっても、その専門分野や対応スタイルは事務所ごとに大きく異なります。
特にクリエイター業は収入形態が多様であり、著作権使用料や海外取引など、一般的な個人事業とは異なる要素も多く含まれます。そのため、単に「近所の税理士」という基準ではなく、クリエイターに強い事務所を見極めることが重要です。
ここでは、信頼できるパートナーを探すうえで欠かせない4つのチェックポイントを解説します。
クリエイター業界への理解と実績があるか
まず最も重視すべきは、税理士がクリエイター業界の特性を理解しているかどうかです。
たとえば、漫画家やイラストレーターであれば画材や資料費、デザイナーであればソフトウェア利用料、動画配信者であれば撮影機材やスタジオ代といった経費が中心となります。これらを正しく経費として処理できるかどうかは、税理士が業界経験を持っているかに左右されます。
実際にクリエイターの顧客を担当した実績があるかを確認することで、適切な申告や節税提案を受けられる可能性が高まります。面談の際には「どんなクリエイターを顧客に持っているか」を聞いてみるのが効果的です。
クラウド会計ソフトに対応しているか
近年はfreeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトの利用が急速に広がっています。
これらを活用すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動連携し、仕訳作業を効率化することが可能です。税理士事務所側でもクラウド会計に対応しているかどうかで、日々の記帳や資料共有のスムーズさが大きく変わります。
特にリモートでのやり取りが多いクリエイターにとって、クラウド会計を導入している税理士は強い味方となるでしょう。導入経験が豊富な事務所なら、ソフトの設定や使い方についてもサポートを受けられるため、経理の効率化につながります。
料金体系が明確で、事業規模に合っているか
税理士に依頼する際は、料金体系のわかりやすさも重要なポイントです。
顧問契約、スポット契約、決算申告のみなど、契約の形態はさまざまですが、費用が不透明だと後々トラブルの原因になります。
事業規模が小さいうちは最低限のサポートで十分ですが、売上が拡大するにつれて継続的な顧問契約が必要になるケースもあります。
見積もりを取る際には、月額報酬・決算料・記帳代行費用などが明確に提示されているかを必ず確認しましょう。また、自身の収入の増減に応じて契約内容を柔軟に変更できるかどうかも、長く付き合ううえでの安心材料となります。
質問・相談がしやすいか
最後に、税理士とのコミュニケーションのしやすさを見極めることが大切です。どれほど知識が豊富でも、専門用語ばかりで理解できない説明をされては意味がありません。
初回面談の際に、疑問点に対してわかりやすく答えてくれるかどうかを確認しましょう。
また、メールやチャットツール、オンライン会議など、自分のライフスタイルに合った相談手段を提供しているかも重要です。
気軽に質問できる環境が整っていれば、確定申告の直前だけでなく日常的な不安も解消できます。信頼できるパートナーとして長期的に付き合うためには、相談のしやすさが欠かせない基準となります。
税理士への相談、いつから検討すべき?
税理士に依頼するタイミングは、人によって大きく異なりますが、共通して「収入や経費の管理が複雑になってきたとき」が目安となります。
たとえば、副業から始めた活動が本業並みに収益を上げるようになった場合や、複数の取引先から継続的に報酬を受け取るようになった場合は、税理士に早めに相談することをおすすめします。
特に注意が必要なのは、課税売上高が一定の水準を超えるタイミングです。原則として、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。この基準を知らずに申告を怠ると、後から追徴課税を受ける可能性があるため、事前に税理士へ確認しておくことが重要です。
また、どのような会社と取引するかによっては、インボイスの登録を消費税の納税義務が発生する前にも行ったほうが良い場合もあります。
青色申告特別控除を受けるには、複式簿記での記帳と決算書の添付に加え、期限内申告が必要です。さらに、e-Taxで申告するか、優良な電子帳簿保存の要件を満たすことで65万円の控除を受けられます。
収入が増えるにつれて「どこまでが経費として認められるのか」「節税のために法人化すべきか」といった判断が必要になるタイミングもあり、こうした分岐点では、経験豊富な税理士の助言を受けることで、自分に合った選択を取ることができます。
結論として、税理士に相談するのは「困ってから」ではなく、「売上が増え始めた時点」や「初めての確定申告に不安を感じた時点」で動くのが理想です。
早めの相談によって無駄な税負担を避けられるだけでなく、長期的な資金計画を立てやすくなり、安心して創作活動に専念できる環境が整います。
まとめ
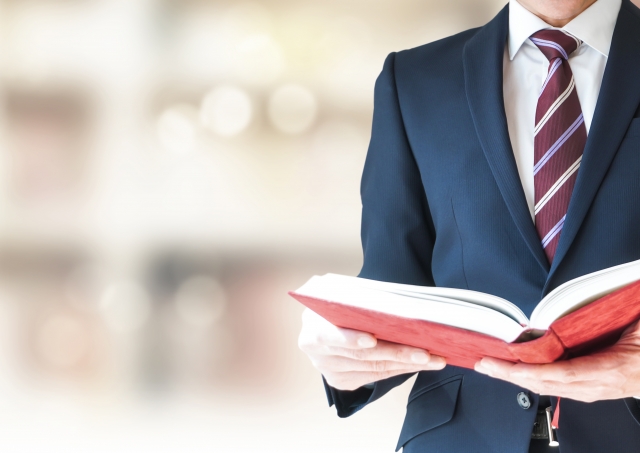
クリエイターにとって、税理士は単なる「経理代行者」ではなく、安心して創作活動を続けるための心強いパートナーです。
確定申告や日々の帳簿付けといった煩雑な作業から解放されるだけでなく、業界特有の経費を踏まえた節税策や、将来を見据えた資金計画についても専門的な助言を受けられます。
さらに、税務調査のリスク軽減や、法人化を含めた事業展開の相談など、幅広い面で支えてくれる存在です。
税理士を選ぶ際には、クリエイター業界への理解やクラウド会計ソフト対応の有無、料金体系の明確さ、相談しやすいコミュニケーション体制といった点を確認することが大切です。
田中貴久公認会計士事務所は漫画家・イラストレーター・Youtuber・Vtuberなどクリエイターの会計・税務を数多くサポートしており、知識・経験が豊富ですので、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。