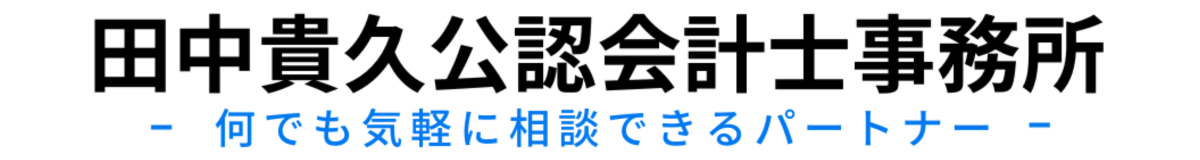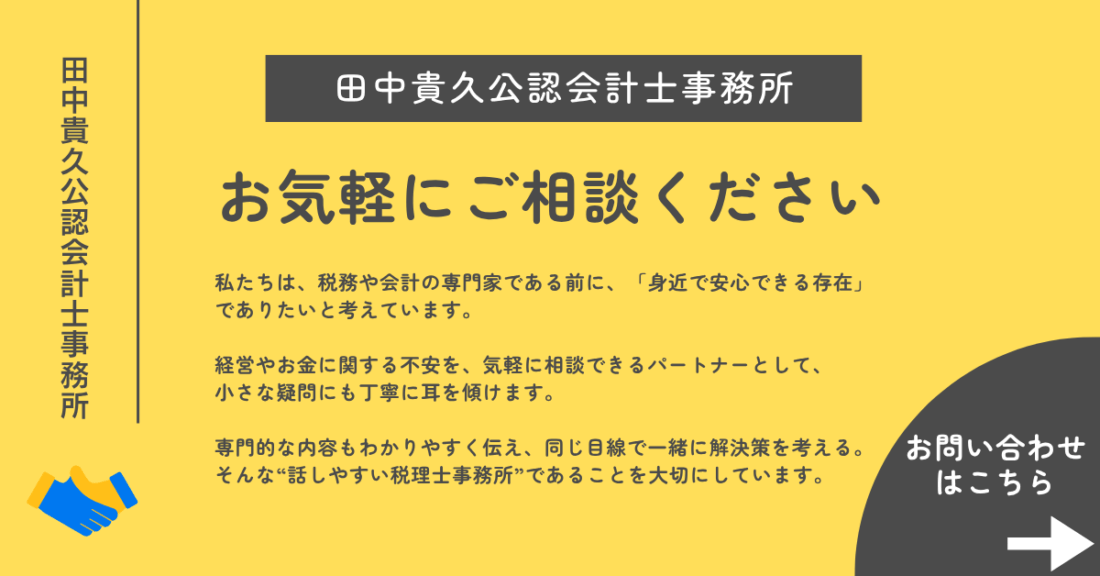pixivFANBOXで収入を得られるようになり、「確定申告はどのように進めれば良いのだろう?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
そこで本記事では、FANBOXで活動するクリエイターの皆様へ、確定申告が必要になる所得の基準や、具体的な申告手順についてわかりやすく解説いたします。
pixivFANBOXの売上、確定申告が必要になるのはいくらから?
pixivFANBOXの収入について確定申告が必要になるかどうかは、クリエイターとしての働き方によって判断基準が異なります。
具体的には、「専業」として活動しているのか、あるいは会社員やアルバイトなどと両立する「副業」なのかによって、確定申告が必要な所得のボーダーラインが変わるのです。
そして、そのボーダーラインを判断する上で重要なのが、「所得」の考え方です。所得とは、売上総額から、活動にかかった必要経費を差し引いた金額を指します。売上そのものではない点に注意しましょう。
専業の場合(所得95万円万円の壁)
専業クリエイターとしてpixivFANBOXなどから売上を得ている場合、pixivFANBOXやそのほかのすべての所得を足した年間の合計所得が95万円を超えると確定申告が必要になります。
副業の場合(所得20万円の壁)
会社員やアルバイト・パートをしており職場で年末調整を受けている場合、pixivFANBOXなどのクリエイター活動は税務上、副業扱いとなります。
副業の場合、年末調整を受けている職場からの所得以外の、すべての所得の年間合計が20万円を超えていると確定申告が必要になります。
pixivFANBOX売上の正しい計上方法
売上を計上する際には、「どの金額を」「どのタイミングで」計上するかが非常に重要です。
この2つを誤ると確定申告の内容に誤りが生じ、後日、追徴課税といったペナルティが課される可能性があるため、注意しましょう。
次からは、pixivFANBOX売上の正しい計上方法を解説します。
手数料が引かれる前の「支援総額」を売上として計上する
pixivFANBOXから振り込まれる金額は、サービス手数料が引かれた後の金額です。しかし、確定申告における売上は、サービス手数料を引かれる前の総額を計上する必要があります。
管理画面から支援金の総額を確認して売上に計上するようにしましょう。
支援金が発生した月に売上を計上する
pixivFANBOXの支援金は翌月20日に振り込まれます。
しかし、売上を計上するのは振り込まれた月ではなく、支援金が発生した月になります。管理画面を確認して何月にいくら支援金が発生しているのか確認しましょう。
確定申告では、その年に発生した売上はその年のうちに計上する必要があります。
特に注意が必要なのが、12月発生・翌1月入金の売上です。入金が翌年であっても、これは12月分の売上として申告しなければなりません。もし申告からもれてしまうと、売上の計上もれとなり、後から追徴課税が課される可能性があります。
pixivFANBOX以外のサービス(BOOTHなど)の売上と合算する
pixivFANBOXだけでなく、BOOTHやpixivリクエストなどからも売上がある場合、すべての売上と合算して、クリエイターの売上を計上します。
確定申告では発生した売上や収入はすべて計上する必要があり、その総額から経費を差し引いて所得を計算するため、合算し忘れたものがないように注意しましょう。
pixivFANBOX活動の経費にできるもの
pixivFANBOXを含めたクリエイターの活動において経費にできるものは、明らかにクリエイター活動の収入を得るために必要な費用のみです。
たとえば、次のようなものが挙げられます。
・イラストなどの製作ソフト購入代金
・文房具や画材代
・資料代
・録音機材の購入代金
・仕事場の家賃
・仕事場の水道光熱費
・インターネット代
ただし、クリエイター活動だけではなくプライベートでも使用しているものの代金や、自宅を仕事場としており家賃や水道光熱費を経費計上する場合、クリエイター活動部分のみが経費として認められます。
そのため、合理的な基準で費用をプライベート用とクリエイター活動用に按分しなければなりません。
たとえば、使用量や使用時間、仕事場として使っている部分の面積などで按分します。自宅兼仕事場として使っており家賃が月10万円で、仕事場として使っているスペースの面積が全体の30%だった場合、3万円(10万円×30%)までを経費計上できます。
pixivFANBOXの確定申告のやり方
pixivFANBOXの確定申告のやり方を、準備から提出までの5つのステップにわけて解説します。
ステップ①:青色申告か白色申告かを決める
pixivFANBOXからの所得を「事業所得」として申告する場合、青色申告をおすすめします。
青色申告では最大65万円まで事業所得から控除でき、もし事業所得が赤字の場合は損失を繰り延べられるなど税制上の特典があります。
青色申告をするには条件があり、事前に「開業届」を税務署へ提出する必要があります。開業届は事業を開始したらできるだけ速やかに提出してください。
さらに、青色申告をしたい初年度は、3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。ただし、1月16日以降に開業した場合は、開業した日から2か月以内に申請書を提出しなければなりません。注意点として、pixivFANBOXからの所得が事業所得と認められるにはいくつか条件があります。基本的な条件としてpixivFANBOXからの売上・経費を記帳し、帳簿の保存をする必要があります。
他の条件として、pixivFANBOXからの所得が例年赤字で、かつ赤字解消のための取り組みを実施していないとされると、雑所得とみなされる場合があるでしょう。
pixivFANBOXの事業所得を常に赤字にしておいて、給与所得と通算して税金を減らすといった使い方はできません。
また、pixivFANBOXからの売上が300万円以下で、副業としてpixivFANBOXでの活動をしている場合、給与所得に対する割合が10%を超えていなければ事業所得ではなく「雑所得」となる可能性があります。雑所得とされた場合は、青色申告の控除は受けられません。
ステップ②:売上と経費をまとめる
年間のpixivFANBOXからの売上と経費をまとめます。特に12月分の売上や経費は振り込みや請求が翌月になる場合があるため、忘れずに計上してください。
経費は実際に存在することや、金額・内容を証明する書類が必要です。計上する経費のレシートや領収書、請求書などを必ず取得して保管しておきましょう。
売上や経費の書類、帳簿などは保管期間が5~7年間のため、7年間は保管してください。もし税務調査が入り、書類の提出を求められた際に、書類をすぐに出せる状態にする必要があります。
会社員やアルバイト・パートの職場でもらう「源泉徴収票」も保管しておき、源泉徴収票に記載されている給与所得や源泉所得税額を確定申告書に反映させます。
ステップ③:確定申告書を作成する
集計した売上や経費をもとに帳簿を作り、確定申告書を作成します。
確定申告書を手書きで作成する方法もありますが、国税庁のWebサイトから「確定申告書等作成コーナー」を利用するか、市販の確定申告ソフトを使う方が作りやすいでしょう。
こうしたツールは必要事項を記入するだけで確定申告書を作成でき、入力漏れや間違いがあった場合は指摘してくれるので安心です。
ステップ④:使える控除をチェックする
確定申告では、所得から控除できる「所得控除」が複数あります。
たとえば、所得2,500万円以下であれば誰でも受けられる「基礎控除」、配偶者や扶養している家族がいる場合の「配偶者控除」や「扶養控除」、生命保険料を支払っている場合に一部を控除できる「生命保険料控除」などがあります。
これらの控除を受けるためには確定申告書に記載し、生命保険料控除など一部の控除では「控除証明書」が必要になります。
また、税額から直接控除できる「税額控除」もあります。
ステップ⑤:申告と納税を行う
確定申告の期限は原則として翌年の3月15日までです。この日までに申告書を提出し、納税まで行わなければなりません。
申告書の提出には、税務署の窓口に持参する方法、郵送する方法、ネットを使ってe-Taxで申告する方法の3つがあります。
その中でも、添付書類が必要なく、自宅で申告できるe-Taxをおすすめします。
e-Taxは画面の指示にしたがって入力すれば申告が完了します。
e-Taxを利用するにはマイナンバーカードを利用する「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法がありますが、ID・パスワード方式はあくまで暫定的な処置であり、いつまで利用できるかわかりません。可能であればマイナンバー方式にしましょう。
マイナンバー方式ではマイナンバーカードと、それを読み込むためのICカードリーダライタを用意する必要があります。
まとめ

確定申告では12月の売上計上もれが起こりやすく、計上もれがあった場合は追徴課税が発生する場合があります。
また、何を経費にしたらいいのか、青色申告をする場合の複式簿記をどうやればいいのかなど、不安や悩みがでてきます。
確定申告で不安があったら、1人で悩まずに専門家である税理士に相談することで、余計な悩みが解消できクリエイター活動に専念できます。
当事務所は、クリエイターへの豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。