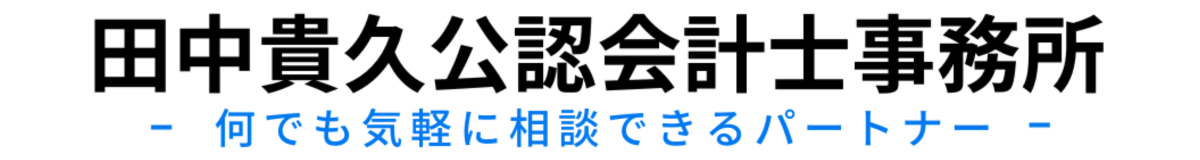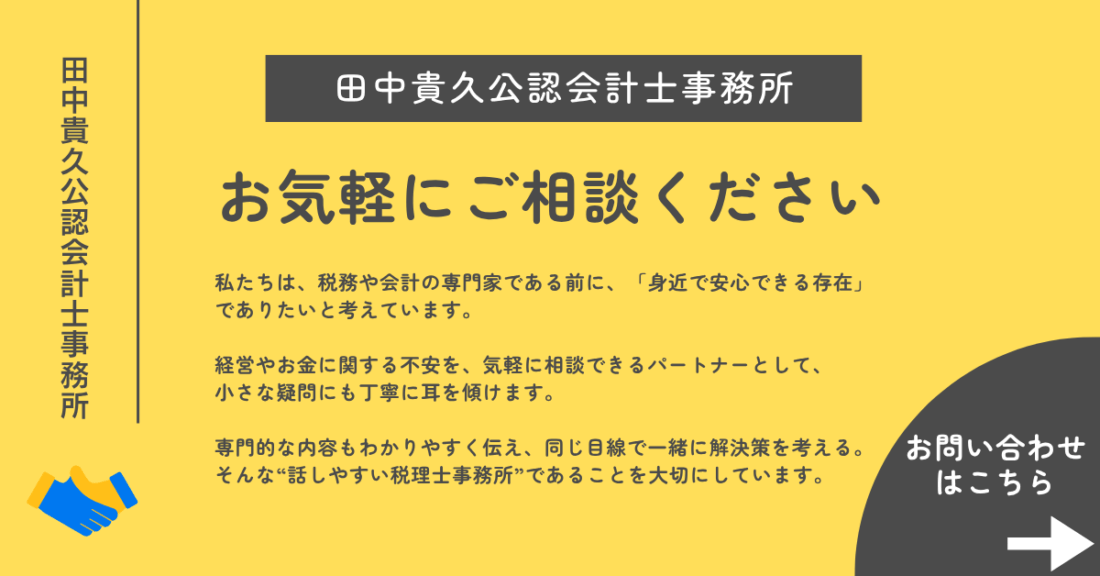フリーランスとして働く人の多くは、2023年10月からはじまったインボイス制度に不安を感じているのではないでしょうか。特に「登録しないと仕事がなくなるのでは?」「登録すると税金が増えて生活が苦しくなるのでは?」といった不安感を抱える方は多いです。
そこで本記事では、インボイス制度の基本から、フリーランスが登録を検討する際の判断基準、さらに税金シミュレーションまで具体的に解説します。
不安を解消し、冷静に判断するための材料としてください。
インボイス制度の基本とフリーランスへの影響
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適正に行うために導入された新しい仕組みです。2023年10月からスタートし、フリーランスを含む多くの個人事業主に影響を与えています。
制度開始以降は「適格請求書(インボイス)」でなければ仕入税額控除が認められなくなり、免税事業者のままでは取引先に不利益が生じる仕組みとなりました。
そのため、取引先から「インボイスに登録してほしい」と求められるケースはしばしばあるのです。しかし、登録すれば消費税の納税義務を負うことになり、これまでよりも手取りが減少する可能性が高まります。
たとえば、年間売上が500万円の場合、インボイス登録により年間で数十万円規模の税負担が発生します。
仕入税額控除により負担は多少軽減されますが、経費が少ないライターやコンサルタントといった業種では影響が大きくなりやすい点に注意が必要です。
さらに、制度導入によって事務的な負担も増えます。
適格請求書の発行、消費税の区分記載、帳簿や領収書の厳格な保存など、これまで以上に正確な経理処理が求められています。そのため、会計ソフトや税理士のサポートの活用なしでは、正確な税務申告がしづらいのが実情です。
制度の目的は消費税の公平な納税を実現することですが、フリーランスにとっては仕事と収入の減少リスクの板挟みになることが多いでしょう。したがって、制度を理解したうえで、登録すべきかを冷静に見極めることが不可欠です。
あなたがインボイス登録すべきか決める2つのポイント
フリーランスがインボイス制度に登録するかを判断する際に重要なのは、一律の答えではなく、自分の事業環境に応じた選択をすることです。
その判断材料として大きく「主な取引先は誰か?」「税負担と事務負担をどう考えるか」という2つの観点が挙げられます。
あなたの主な取引先は誰ですか?
インボイス登録の判断で最も重視すべきは「取引先のタイプ」です。
取引先が課税事業者であれば、仕入税額控除をするためにインボイスを必要とします。そのため、あなたがインボイス未登録の場合、登録済みの事業者に仕事を回されるリスクが高まります。
一方で、取引先の多くが免税事業者や一般消費者であれば、インボイス未登録でも影響はほとんどありません。
たとえば、BtoCのクリエイターや個人向けの講師業などが挙げられます。登録せずに活動を続けたとしても顧客が離れないのであれば、収入減少のリスクはほとんどないと判断可能です。
あなたの主要顧客層が誰であるかを見極め、登録すべきかを判断しましょう。
自身の税負担と事務負担をどう考えますか?
インボイス制度に登録することで、フリーランスは消費税の納税義務を負うことになります。
これまで免税事業者として消費税を納めずに済んでいた人にとっては、売上の10%を納税する必要が生じるため、手取りが減る点は無視できません。
また、事務的な負担も増加することも踏まえておくことが必要です。具体的には、適格請求書の発行、仕入税額控除の計算、消費税申告書の作成など、新たな作業が加わることになります。
こうした経理に慣れていないフリーランスにとっては、大きなストレスとなるかもしれません。
したがって「取引先からの要求」と「自身の負担増加」のバランスをどう取るかを検討し、インボイス登録をするか判断してください。
【税金シミュレーション】インボイス登録で税金はいくら増える?
現在免税事業者の方は、インボイス登録するとどれくらいの税金を負担することになるかが気になるのではないでしょうか。ここでは、年間売上が500万円のフリーランスを想定して、具体的にシミュレーションしてみます。
まずは単純計算をしてみましょう。免税事業者の場合には売上500万円がそのまま収入となります。しかし、インボイス登録をすると、売上にかかる消費税の納税義務が発生し、10%なら約45万円を負担することになるのです。
次に、経費額を考慮した際の、最終的な納税額をシミュレーションをしてみましょう。
| 年間の経費 | 仕入税額控除できる額 | 最終的な納税額 |
|---|---|---|
| 年間50万円の場合 | 約4.5万円 | 約40.5万円 |
| 年間100万円の場合 | 約9万円 | 約36万円 |
| 年間200万円の場合 | 約18万円 | 約27万円 |
このように、同じ500万円という売上でも、経費の割合によって最終的な納税額は大きく変わります。経費の少ない業種は影響が大きく、経費の多い業種では比較的負担が抑えられる傾向があります。
具体的な数字を踏まえて、自分の事業にとっては登録したほうがいいのかを吟味することが大切です。
なお、2026年9月末までは経費の額にかかわらず、売上税額の2割だけを納めればよいという特例が活用できる場合があります。経費計上できる費用が少ないことがインボイス登録の懸念事項となっている方は、2割特例の活用を検討するといいでしょう。
参照:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
インボイス登録後の確定申告のやり方
インボイス制度に登録すると、従来の所得税の確定申告に加えて、消費税の申告・納付が必要となります。
まず、売上に応じて発行した適格請求書や領収書を整理し、消費税額を正確に計算してください。その際、経費として支払った仕入や外注費にかかる消費税については、仕入税額控除が適用できます。節税につなげるための証憑となるため、領収書や請求書はきちんと保管しておきましょう。
実務上は、会計ソフトを活用して取引ごとに消費税区分を登録しておくと、決算時にスムーズに申告書が作成できます。確定申告直前になって慌てることのないよう、こまめに登録しておくことをおすすめします。
また、フリーランスにとっては納税資金の準備も重要です。消費税は売上に上乗せして受け取っているお金であることを忘れてはいけません。日頃から消費税分を分けて管理しておくと、申告時の資金繰りで慌てずに済みます。
まとめ

インボイス制度はフリーランスにとって大きな転換点であるため、登録するかは「取引先の状況」と「自身の事業戦略」で判断することが必要です。
登録すれば仕事の継続性を確保できる一方、税負担や事務作業の増加は避けられません。そのため、税額シミュレーションを行い、自分の事業モデルに合った選択をすることが不可欠です。
しかし、インボイス登録をすべきかで迷う方は多いでしょう。自分で判断しきれない場合や、消費税の計算や申告方法に不安がある場合には、フリーランスに強い税理士に相談するのが最善の方法です。
専門家のサポートを受けることで、制度対応だけでなく節税や資金繰りの面でも安心感を得られます。
田中貴久公認会計士事務所は、クリエイターを中心としたフリーランスの会計・税務に強い事務所です。インボイスの登録をはじめ、会計・税務にお困りの場合には、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。