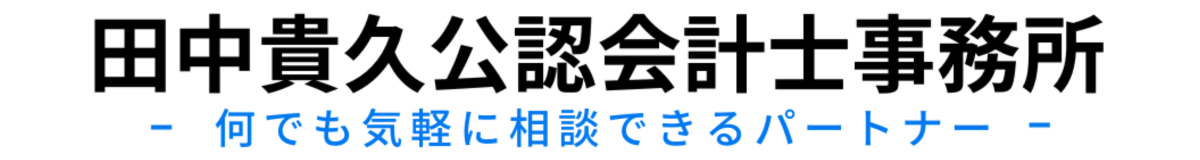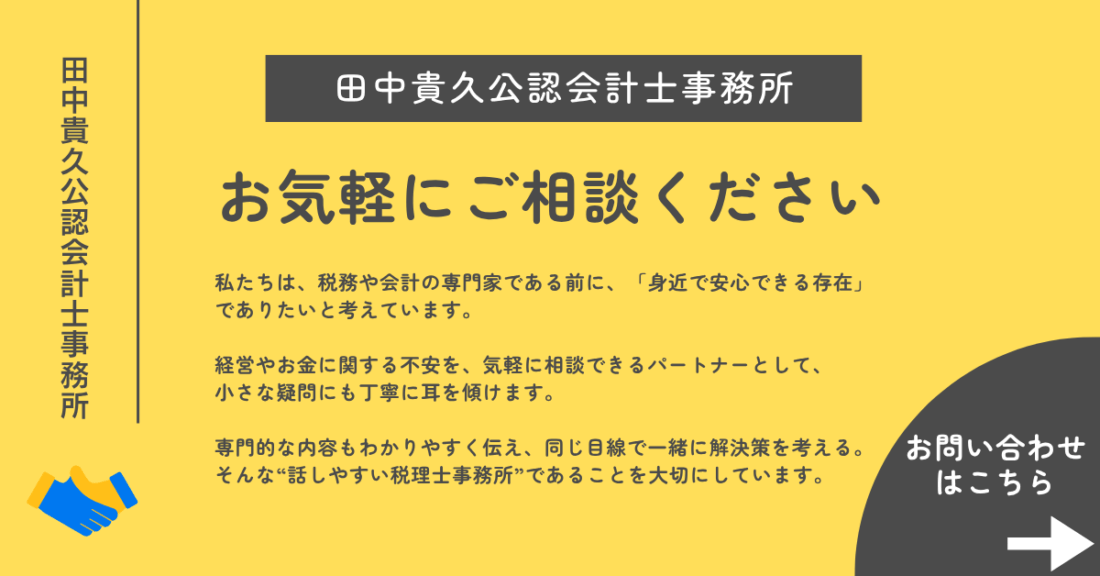フリーランス1年目の方にとっては、初めての確定申告が不安の種になりがちです。「そもそも何から準備すればよいのか」「必要な書類はどれなのか」と迷ってしまう方も少なくありません。
そこで本記事では、確定申告の基本的な流れから準備・書き方・提出方法まで、初心者でも理解できるように詳しく解説します。
【準備編】フリーランスの確定申告、1年間の準備
フリーランスの確定申告は「申告時期だけ行う作業」と誤解されがちですが、実際には1年間を通じた日常的な準備が成功の鍵を握ります。
ここでは、確定申告に向けて、日頃行っておきたい準備を解説します。
日々の記帳:確定申告ソフト・アプリの活用
確定申告を効率化するために最も役立つのが、会計ソフトやアプリの活用です。銀行口座やクレジットカードと連携すれば、自動で取り引きを仕訳してくれるため、手入力での事務負担や計算ミスによる修正作業などを削減できます。
また、レシートを撮影するだけで仕訳に必要な情報が自動で取り込めるスマホアプリは利便性が高く、外出先でも経費管理が可能です。さらに、青色申告用の複式簿記に対応しているソフトを選べば、確定申告書類を自動で作成できるのが大きなメリットです。
ツールはいくつもあるので、まずは無料トライアルで試し、自分の業務スタイルに合ったものを選んでみてください。
必要書類の保管:領収書・請求書の整理術
確定申告では、領収書や請求書などの証憑を提出する必要はありません。しかし、税務署から求められた際に提示するために、7年間の保管義務があります。効率よく管理するには、月ごとにクリアファイルへ分類したり、スキャンしてクラウドに保存したりする方法が有効です。
請求書は発行日や入金日を明確に記録し、領収書は「何に使った経費か」をメモしておくと後で迷いません。
デジタル化すれば検索が容易になり、確定申告ソフトとも連携可能です。整理を怠ると経費計上の漏れや誤りにつながるため、日常業務のなかで習慣化することをおすすめします。
【申告方法の選択編】青色申告?白色申告?
フリーランスが確定申告を行う際には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶべきかを、ここで解説していきます。
青色申告のメリットと必要な手続き
青色申告の最大の魅力は「節税効果」です。複式簿記を用いた帳簿を作成し、所定の条件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。これにより所得税の負担を大きく軽減できます。
また、赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる制度も利用可能です。事業を始めたばかりのフリーランスには大きな安心材料となるでしょう。
ただし、青色申告を利用するには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、開業後2ヶ月以内または申告する年の3月15日までに手続きを行わなければなりません。
白色申告のメリットと注意点
白色申告は事前の申請が不要で、帳簿も簡易的な単式簿記で済むため、初めて確定申告を行う人にとっては利用しやすい制度です。特に収入が少ない段階では複雑な帳簿を作らずに申告できるため、心理的なハードルも低いと言えます。
しかし、青色申告のように控除は大きくなく、節税効果は限定的です。さらに、2014年以降は白色申告であっても帳簿保存義務が強化されたため、収入や経費の記録はしっかりと残すことが必要になりました。
短期的には便利でもフリーランスとして安定した収入を目指すのであれば、将来的には青色申告への移行を検討することが望ましいでしょう。
【作成編】確定申告書の書き方と計算
確定申告書に必要事項を正確に記入しなければ、税額計算に誤りが生じたり、控除が適用されなかったりする可能性があります。
ここでは適切な書き方と、所得の算出方法について解説します。
収入・経費の集計と所得の計算
まずは1年間に得た売上を合計し、そこから事業に必要な経費を差し引いて「所得金額」を算出します。収入には請求書ベースの売上や振込額を集計し、経費には仕事に必要な通信費、交通費、消耗品費などを含めます。
青色申告の場合は複式簿記で、白色申告の場合は単式簿記でまとめるのが基本です。
収入と経費を正しく記録していないと、本来認められるはずの経費を申告できず、結果として税負担が増えてしまいます。不安な方は、集計から所得計算までスムーズに行える会計ソフトを活用し、ミスがないように対策を取ることを推奨します。
各種控除の記入
確定申告書には、所得から差し引ける「所得控除」を記入する欄があります。代表的なものに社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除や扶養控除などがあり、これらを漏れなく記載することで課税所得を圧縮できます。
その際、控除の対象となる支払いを証明する書類(控除証明書など)は、申告書の作成時に手元に用意しておくことが大切です。
特にフリーランスは給与天引きがないため、自分で把握して申告に反映させなければなりません。控除を漏らすと納める税金が増えるため、確認しながら記入すると安心です。
給与所得がある場合の書き方
副業としてフリーランス活動をしている方は、会社からの給与所得も確定申告に含める必要があります。確定申告書の「給与所得」欄に源泉徴収票の内容を転記し、事業所得と合算して税額を計算します。
この際、給与から既に源泉徴収された所得税額を申告書に記入することで、二重課税を防ぐことができます。
副業の規模が小さい場合でも申告義務は発生することが多いため、源泉徴収票を紛失しないように管理しておきましょう。
また、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)など、給与所得者向けの控除制度も併用できるため、忘れずに申告して節税につなげてください。
【提出編】スマホで完結!e-Taxがおすすめ
確定申告書の作成が終わったら、いよいよ提出です。提出方法は大きく分けて「e-Taxによる電子申告」「印刷して郵送」「税務署の窓口に持参」の3種類があります。
なかでも便利なのはスマホやPCから送信できるe-Taxで、24時間いつでも提出可能なため、忙しいフリーランスにとって強い味方です。提出期限は通常3月15日までなので、余裕を持って準備しておきましょう。
以下、提出方法について詳しく確認してください。
e-Taxでの電子申告
e-Taxは国税庁が提供するオンライン申告システムで、スマホやパソコンからインターネット経由で手続きを完結できます。マイナンバーカードを使ったログインや、ID・パスワード方式による利用が可能で、申告書を自宅から送信できるのが大きなメリットです。
青色申告特別控除65万円を受けるためには「e-Taxによる申告」または「電子帳簿保存」が必須条件となるため、節税を考えるなら電子申告は避けて通れません。
さらに、還付金の振り込みも紙提出より早く処理される傾向があり、利便性と実益の両方を兼ね備えています。
初めて利用する場合は国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」から案内に沿って進めれば問題なく行えます。
郵送・窓口での提出
従来の方法として、印刷した申告書を郵送するか、税務署の窓口へ直接提出する方法もあります。郵送の場合は提出期限の当日消印が有効となるため、期日ギリギリに慌てないよう余裕を持って送るのが安心です。
窓口提出では、職員に確認してもらえる安心感がありますが、確定申告の時期は非常に混雑するため、長時間待つ可能性があります。青色申告の65万円控除は紙提出では適用されないため、最大限の節税を狙うならe-Taxを利用する方が有利です。
ただし、マイナンバーカードやICカードリーダーを持っていない方、ネット環境に不安がある方は、紙での提出も選択肢の一つとなります。
【納税・還付編】税金はいつ払う?
確定申告を提出した後は、税金の納付や還付金の受け取りが待っています。納付が必要な場合は、申告書に記載された金額を期限までに支払わなければなりません。通常、所得税の納期限は3月15日と定められており、振替納税を利用すれば4月中旬頃に自動引き落としが行われます。
納付方法は銀行や税務署窓口での現金払い、クレジットカード、コンビニ、インターネットバンキングなど多様化しているため、自分に合った方法を選べます。
一方、払いすぎた税金がある場合は「還付」として銀行口座に振り込まれます。目安は紙での申告なら1ヶ月~1ヶ月半、e-Taxでの申告なら3週間程度です。
納税・還付のスケジュールを把握しておくことで、資金繰りにも余裕を持たせられるでしょう。
まとめ

フリーランスにとっての確定申告は、一見ハードルが高く思えるものの、流れを理解して準備を整えれば自分でも十分に対応可能です。日々の記帳や領収書の整理を習慣化し、会計ソフトやe-Taxを活用することで、効率的に作業を進めましょう。
申告を怠れば延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されるリスクもあるため、正しい知識と手続きを意識することが大切です。フリーランスとして安心して活動を続けるために、毎年の確定申告をスムーズにこなせる体制を整えておいてください。
なお、「税金が思った以上に高い」と感じたり、複雑な仕訳や控除の判断に不安があったりする場合は、専門家へサポートを依頼してみてはいかがでしょうか。
フリーランスの会計・納税に実績のある田中貴久公認会計士事務所なら、確定申告や税務に関する不安を解決できるよう支援いたします。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。