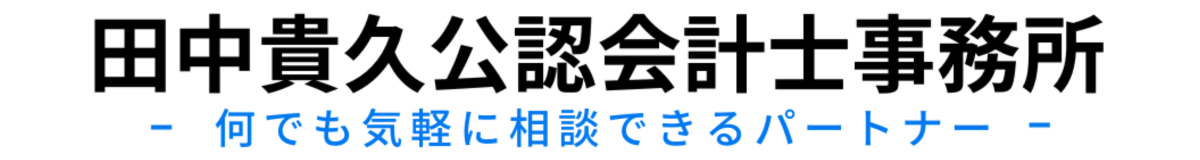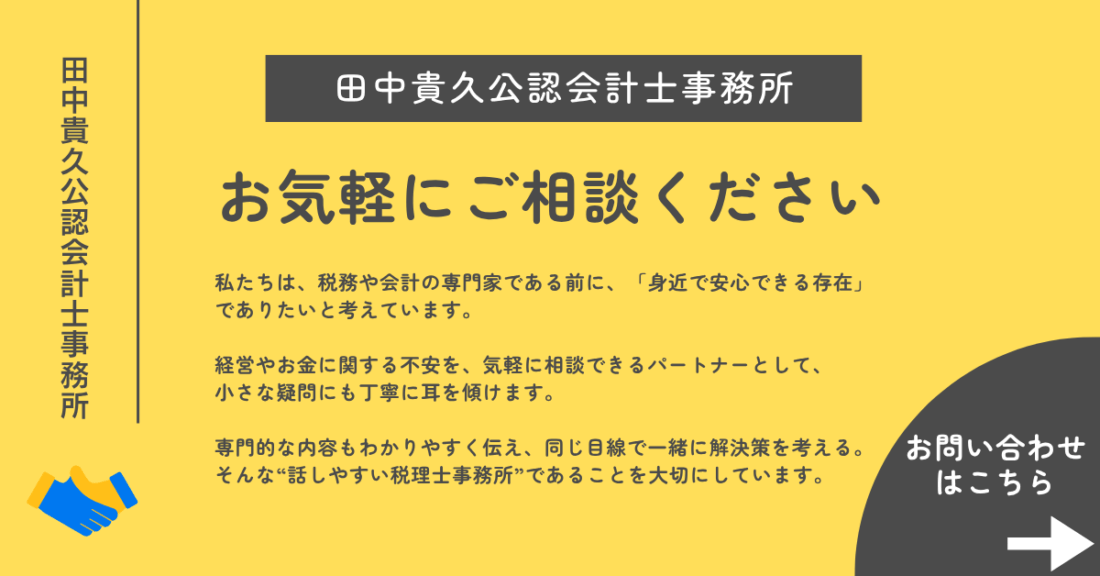自ら案件を獲得し、契約や納期管理を行いながら開発業務を進められるフリーランスエンジニアは、自由度の高い働き方ができるのが魅力です。その反面、会社員時代にはなかった税金支払いや確定申告に関して、課題に感じる方は多いでしょう。
特に、経費の範囲や契約形態ごとの税務上の扱いなどを正しく理解しなければ、余計な税負担やトラブルにつながりかねません。
そこで本記事では、フリーランスエンジニアが押さえておくべき税務の基礎知識と、スムーズに確定申告をするためのポイントを解説します。
【経費】フリーランスエンジニア特有の経費にできるもの
フリーランスエンジニアにとって、経費計上は節税を実現するうえで最も重要なポイントです。
経費とは、業務遂行に必要な支出を指し、正しく申告すれば所得税や住民税の負担を軽減できます。代表的なのは、開発用パソコンやモニター、周辺機器といったハードウェアの購入費用です。
これらは業務効率に直結するため、経費として計上できます。また、GitHubやAWS、クラウドストレージなどのサブスクリプション費用も、事業利用が明確であれば経費として取り扱うことが可能です。
在宅勤務が多いエンジニアなら、通信費や電気代、家賃の一部を「家事按分」して計上できます。例えば、作業部屋が自宅の30%を占めている場合、家賃や光熱費の30%を経費として申告することが認められます。
さらに、技術書やオンライン講座、資格試験費用も「自己研鑽」として業務関連性を説明できれば経費計上が可能です。打ち合わせや勉強会に参加する際の交通費やカフェでの飲食代も、業務上の利用であれば認められることが多いです。
ただし、プライベートでの利用割合が高い費用を強引に経費にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。領収書や利用明細を保存し、「なぜ業務に必要だったか」を説明できる形にしておくことが不可欠です。
フリーランスエンジニアは業務の特性上、ITツールや学習投資に支出が集中することが多いでしょう。それらを抜け漏れなく経費計上することが、税負担の軽減につながります。
【契約形態】SES契約における税務上の注意点
フリーランスエンジニアの中には、「SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)」を締結する方もいるでしょう。
SES契約は業務委託の一種ですが、成果物の納品ではなく「労務提供」が中心となります。稼働時間に応じて報酬が発生する仕組みであるため、請負契約と異なり、成果物の完成責任は負いません。
しかし、実態としては発注企業の指揮命令下で働くケースも多く、形式上フリーランスであっても「雇用に近い働き方」とみなされることがあります。
この場合、税務上は事業所得として申告するのが一般的ですが、契約内容や業務の実態によっては「労働者性」が認定され、源泉徴収や社会保険加入を求められるリスクが生じます。
特に契約書に業務範囲や成果物の定義が曖昧に記載されていると、後のトラブルにつながりかねません。フリーランスエンジニアとしては、報酬形態や支払い条件、経費負担の有無を契約段階で明確にしておくことが重要です。
また、SES契約は「安定収入を得やすい」反面、経費が少なく所得が高くなりがちです。そのため、青色申告による控除や小規模企業共済・iDeCoといった節税策を併用して税負担を軽減することが望まれます。
長期的には請負契約や自社サービス開発など、より独立性の高い契約形態へシフトすることも検討すべきです。SES契約を続ける場合には、税務・法務リスクを理解し、必要に応じて税理士や弁護士に相談することで安心して働ける環境を整えましょう。
フリーランスエンジニアの確定申告、効率化のポイント
フリーランスエンジニアの確定申告を効率化するには、日々の経費管理が欠かせません。しかし、準備段階にすべきことの
イメージが湧かない方もいるでしょう。
ここでは、確定申告を効率化する手法を解説します。
まずは「開業届」を提出し、青色申告の準備を
フリーランスエンジニアとして活動し始めたら、最初に税務署へ「開業届」を提出しましょう。
開業届とは、個人事業主が新たに事業を開始したことを、税務署に知らせる書類のことです。開業届を提出し、青色申告承認申請書を提出することで、所得税の申告について青色申告を選択できるようになります。
青色申告を利用すれば、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除といった大きな節税メリットを享受できます。さらに、家族を従業員として雇った場合に、給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」など白色申告にはない制度も利用可能です。
ただし、青色申告をするには、正確な帳簿付けなどの要件を満たす必要があります。
特に電子帳簿保存法の改正により、請求書や領収書を電子データで保存するルールが強化されました。対応していないと控除が受けられないリスクもあります。
開業届が未提出の場合、これらの制度は一切活用できず、結果的に税負担が大きくなってしまいます。独立後はできるだけ早い段階で開業届を提出し、青色申告の準備を整えておくようにしましょう。
会計ソフトの活用で、経費管理を自動化
フリーランスエンジニアは案件対応で忙しく、経理に割ける時間が限られるでしょう。そのため、会計ソフトを導入して経費管理を自動化することが有効です。
freeeやマネーフォワード、弥生会計といったクラウド型ソフトは、銀行口座やクレジットカード、電子マネーと連携できます。入出金データを自動で取り込んだうえで、AIが仕訳を提案してくれるため、日常的な入力作業や記帳の手間を大幅に削減できるのが利点です。
さらに、領収書や請求書をスマホで撮影すると、OCR機能により内容が読み取られ、自動的に帳簿へ反映されます。これにより、紙の領収書の管理から解放され、電子帳簿保存法にも対応可能です。
ソフトによっては、確定申告書や消費税申告書を自動生成し、そのままe-Taxに提出できる機能も備わっているため、申告時の負担を軽減できます。
また、クラウド会計ソフトを使えば、税理士とデータをリアルタイムで共有できるため、経理状況の確認やアドバイスを受けやすくなるのが魅力です。特にITスキルが高いエンジニアにとっては、こうしたデジタルツールを最大限に活用することが効率化の鍵を握ります。
経理作業に追われず、本業の開発業務に集中できる環境を作ることこそ、フリーランスにおける会計ソフト導入の最大のメリットといえるでしょう。
エンジニアに強い税理士の選び方
確定申告を正確かつ効率的にするには、税理士のサポートを受けるのがおすすめです。
ただし、どの税理士でも良いわけではなく、フリーランスエンジニア特有の契約形態や経費処理に理解があるかを基準に選びましょう。
SES契約や請負契約の違い、クラウドサービス利用料やソフトウェア購入費用の扱いなど、IT分野の知識がある税理士であれば、適切なアドバイスをしてくれます。
さらに、freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトに精通している税理士を選ぶと、スムーズにデータ共有や申告作業が進みます。
そのうえで、節税策や資金繰りのアドバイス、インボイス制度や電子帳簿保存法といった、最新の制度変更への対応をサポートしてくれる税理士に絞り込みましょう。
相談しやすい人柄かレスポンスが速いかも含め、安心して本業に集中できるような税理士を選んでください。
まとめ

フリーランスエンジニアが確定申告を行ううえで重要なのは、特有の経費を適切に計上し、契約形態ごとの税務リスクを理解することです。
特にSES契約は雇用と業務委託との区別が難しく、報酬や経費の扱いを契約書で明確にしておくことが必要です。
また、節税効果を高めたい場合には、開業届を提出したうえで青色申告を選択することが求められます。クラウドの会計ソフトを活用し、日々の経理を効率化しておきましょう。
しかし、税務の制度やルールは改正されることが多く、個別の事情によって最適な判断は異なります。そこで頼りになるのが、エンジニアに強い税理士の存在です。
税理士のサポートを受ければ、節税対策や資金繰りの相談に加え、制度変更への対応がスムーズにできるため、安心して本業に集中できます。
田中貴久公認会計士事務所は多数のフリーランスエンジニアの税務・会計を支援した実績があるので、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。