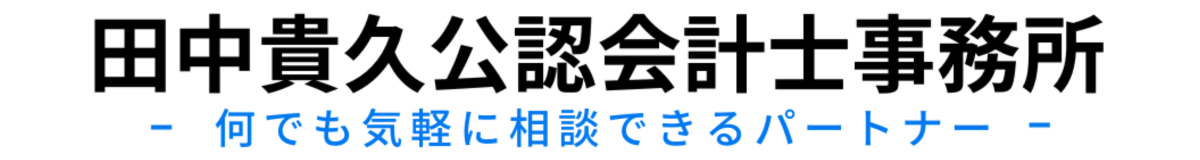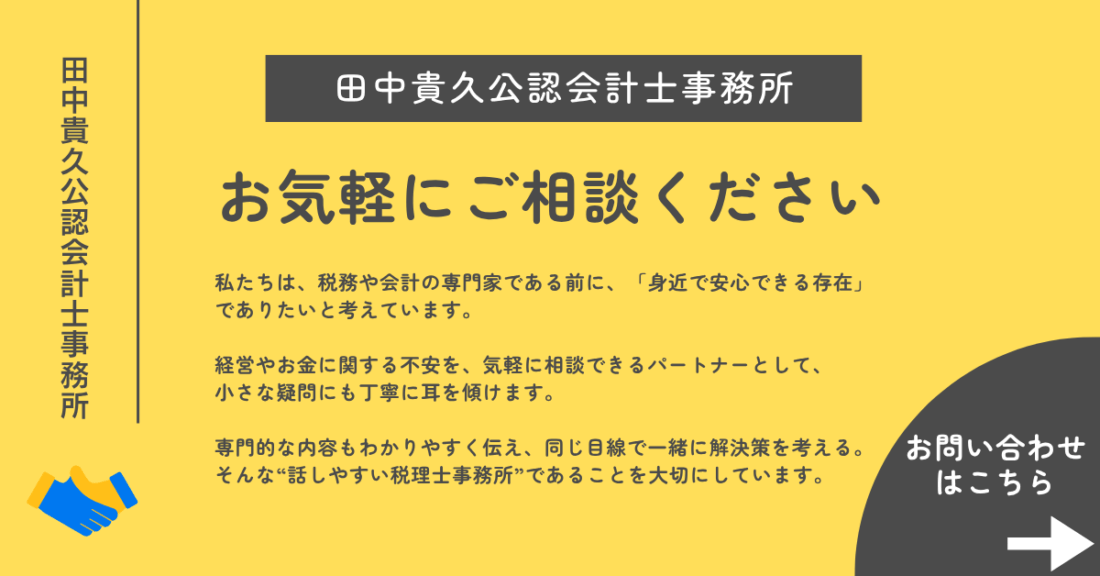クリエイターとして活動を始めた方のなかには、「税金のことがよくわからない」という不安を抱えている方は少なくないでしょう。
税金に関する知識が不足していると、適切な申告ができず思わぬ追徴課税につながったり、納税時期に資金が用意できなかったりするかもしれません。
そこで本記事では、クリエイターにとって身近な税金の種類と基本的な考え方を整理し、確定申告をどのように進めるべきかをわかりやすく解説します。
クリエイターに関わる4つの税金とは?
クリエイターが納める可能性のある主な税金は、「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4種類に大別されます。
これらは事業の規模や収入額によって課税の有無が変わり、適用される税率や納付先も異なります。
たとえば、所得税は国税である一方、住民税や個人事業税は地方自治体に納める税金です。消費税は取引規模に応じて納税義務が発生します。
こうした税金の特徴を理解しておくことは、将来の資金繰りや事業拡大を見据えたうえでも不可欠です。ここからは、それぞれの税金がどのように課税されるのかを詳しく見ていきます。
所得税
所得税とは、1年間に得た「所得」に対して課される税金です。課税対象は「収入-必要経費」で算出される所得で、そこから基礎控除や社会保険料控除などの各種控除を差し引いた残額に対し、5~45%までの累進税率が適用されます。
たとえば、デザインや執筆、動画制作などから得た報酬はすべて収入です。収入から機材費や取材費などの必要経費を差し引いた残りが課税対象となります。
副業の場合は20万円、専業の場合は令和7年からは95万円(令和6年までは48万円)を超えると確定申告の義務が生じます。この場合、1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の確定申告をもって3月15日までに納税する仕組みです。
納付方法を誤ると延滞税が発生するため、売上の金額に関わらず早い段階から仕組みを理解しておきましょう。
住民税
住民税とは、前年の所得を基準に都道府県と市区町村に納める地方税です。所得税と異なり、確定申告を行った情報が自治体に通知され、それをもとに住民税額が決定されます。
原則として所得の1割程度が課税されるため、前年に大きく稼いだ場合には、翌年の住民税が高額となる点には注意が必要です。
納付は6月以降に通知され、普通徴収で年4回に分けて支払うか、特別徴収で給与から天引きされる仕組みから選べます。副業の場合には、特別徴収だと会社に副業をしているのが知られることがあるので、これを避ける場合には普通徴収を選択することをおすすめします。
ただし、住民税を普通徴収で納める場合には、自分で各期の納期限までに支払いが必要です。遅れると延滞金や督促の対象となるため、納税資金は確保しておきましょう。
消費税
消費税とは商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
たとえば、イラストや映像制作の仕事で高額な売上を得た場合、翌々年に消費税を申告・納付する必要が出てきます。
仕組みとしては、クライアントから受け取った消費税額から、自分が経費として支払った消費税額を差し引いて納付する「仕入税額控除」が基本です。
なお、インボイス制度が開始されたことにより、課税売上高が1,000万円未満の免税事業者であっても、取引先からインボイス登録を求められるケースが増えています。インボイス登録をすると1,000万円未満であっても消費税の申告・納税が必要です。
登録すべきかは、クリエイターとしての活動方針によっても異なるので、慎重に検討しましょう。
個人事業税
個人事業税は、都道府県に納める地方税で、法律で定められた70業種に該当する事業に課されます。
クリエイターに関係の深い「デザイン業」や「広告業」は課税対象となる代表例です。
課税対象となる所得が290万円を超えると課税が始まり、税率は3~5%程度とされています。
住民税や所得税とは異なり、経費を差し引いたうえで計算される点は同じです。しかし、クリエイターとしての報酬よりも時間給として支払われるような場合、個人事業税の対象から外れることもあります。
クリエイターは自分の事業内容が該当するかを確認し、課税対象となる場合は資金繰りに支障が出ないよう備えておきましょう。
税額を決める「所得」と「経費」の基本
税金の計算においてもっとも重要なのは、「所得」と「経費」の考え方です。
所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指し、この金額が各種税金の課税対象となります。
たとえば、イラスト制作や動画編集などの報酬が売上にあたり、そこから制作に使用したパソコンやソフトウェアの購入費、取材や打ち合わせにかかった交通費などが経費として認められます。
経費として計上できるかの基準は「事業に必要な支出か」で判断してください。プライベートな出費は含められませんが、混在している場合には、按分割合によって経費にすることが可能です。
適切に経費を記録することで課税所得を正しく算出でき、結果として納める税金を抑えられます。なお、日々の取引を領収書やクラウド会計ソフトで整理しておくと、確定申告時の負担を大幅に軽減できるため、こまめな計上を心がけましょう。
クリエイターとして長く活動を続けるには、所得と経費の基本を正しく理解して管理することが欠かせません。
税金を申告する「確定申告」の流れ
クリエイターが所得税を納める際には、毎年「確定申告」が必要です。
確定申告の流れは大きく分けて、帳簿や領収書の整理、収入と経費の集計、申告書の作成、そして税務署への提出というステップで構成されます。
まず、1年間の売上や経費を正確に集計し、所得を算出します。その後、申告方法を選択し、それぞれの形式に沿って申告書を作成してください。
なお、青色申告を選ぶと最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除といったメリットがあるため、事業として本格的に活動するクリエイターには大きな利点があります。
ただし、青色申告を選択する場合は、開業届と青色申告承認申請書を事前に提出しておく必要があります。
申告書はe-Taxを利用してオンラインで提出できるほか、税務署窓口や郵送での提出も可能です。申告期限は原則として翌年の3月15日であり、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課されるため注意が必要です。
確定申告の流れを理解し、計画的に準備を進めることで、税務リスクを回避しましょう。
確定申告、自力で行う?税理士に頼む?
確定申告を行う方法には、自分で作業を進めるか、専門家である税理士に依頼するかの2つの選択肢があります。
自力で行う場合は、会計ソフトや国税庁の作成コーナーにおける相談を活用すれば比較的スムーズに進められるでしょう。しかし、経費の判断や控除の活用など専門知識を求められる場面では迷いやすいのが難点です。
一方、税理士に依頼すれば正確な申告や節税のアドバイスを受けられ、結果的に時間や労力を大幅に節約できます。その結果、創作活動に専念できる時間が多くなるのが利点です。
昨今のクリエイターとしての活動にあたって、クラウドソーシングサービスを利用したり、SNSから収益をあげることができたりするなど、収益源が多種多様になっています。会計処理が煩雑なため、計上の際には注意が必要なことがあるでしょう。
さらに、会計に関する法令・制度は頻繁に改正されるため、常に新しい制度に基づいて会計処理・確定申告をすることが求められます。
複雑な会計処理やインボイス制度対応など、新しい制度への不安がある場合は、税理士の力を借りると負担を軽減できる可能性が高いので検討してみることをおすすめします。
まとめ

クリエイターとして活動を続けていく上で、税金に関する知識は、事業を守り成長させるための欠かせません。
所得税・住民税・消費税・個人事業税といった各種税金の仕組みを理解し、売上や経費を正しく管理することで、余計な税負担を避けられます。また、確定申告の流れを把握しておけば、申告期限に間に合うよう計画的に準備できるでしょう。
自力での申告に限界を感じたときや、節税・資金繰りのアドバイスを受けたいときには、税務の専門家である税理士に相談してみてはいかがでしょうか。税務の不安を解消できるため、安心して創作活動に集中できる環境が整います。
田中貴久公認会計士事務所なら、漫画家やイラストレーター、Youtuberなどのクリエイターの会計・税務をサポートした実績が豊富です。クリエイターに強い税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。