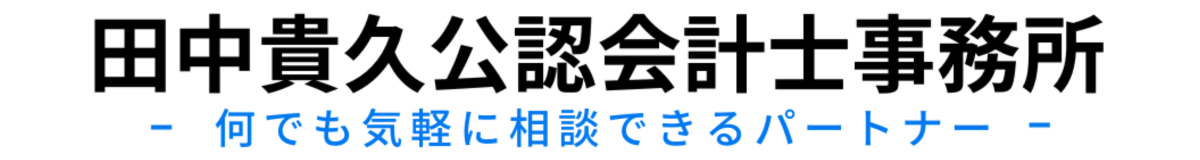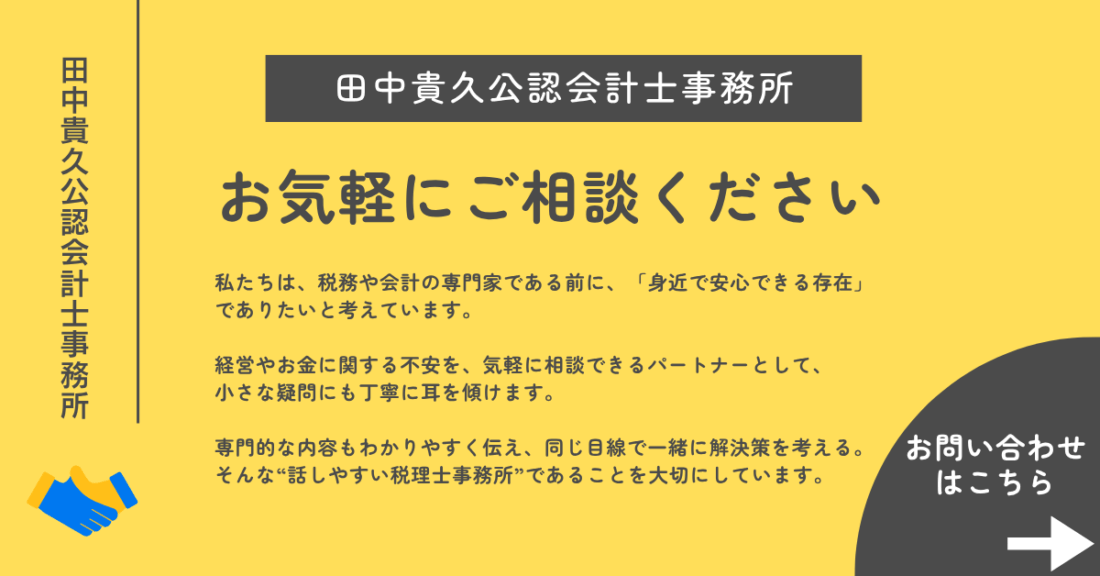はじめて確定申告をするクリエイターの方の中には「どこから手を付ければよいの?」「経費はどこまで認められるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
確定申告は、基本の流れや経費の考え方さえ理解できれば、作業は難しいものではありません。
そこで本記事ではクリエイターの確定申告について、副業・専業で変わる申告義務の基準、開業届と青色申告の関係、押さえておきたい典型的な経費項目などについてやさしく解説します。
そもそもクリエイターの確定申告とは?
確定申告とは、1年分の収入と経費を集計し、納める所得税の額を確定する手続きです。以下のように、副業か専業かで「申告が必要になる所得ライン」が異なります。
・副業:所得20万円超え
・専業:所得95万円(基礎控除)を超え
まずはどちらに当てはまるかを確認し、必要書類を揃えることから始めましょう。
副業の場合:所得20万円の壁
会社員・アルバイトをしつつ収益を得る副業クリエイターは、1年間の「所得(=収入-経費)」が20万円を超えたら確定申告が必要です。
給与で源泉徴収されていても、このラインを超えれば申告義務が生じます。見込み収入が伸びやすい開始1年目こそ、日々の記帳とレシート保存を徹底し、期末にあわてない体制をつくりましょう。
また、所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要です。所得の20万円の壁はあくまで所得税に関する話であるため、住民税の申告とは異なります。
なお、住民税の徴収方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類から選択可能です。
特別徴収の場合、副業分の住民税も本業の給与から天引きされることになります。会社に副業していることを隠しておきたい場合は、副業分の住民税は普通徴収で納めるようにしましょう。
専業の場合:所得95万円の壁
専業クリエイターとして活動している場合、年間の合計所得が95万円(令和6年までは48万円)を超えると確定申告が必要です。この95万円という基準は所得税「基礎控除」の金額であり、給与所得者における所得の20万円の基準とは異なります。
たとえば、イラストの報酬が130万円あり、経費が32万円かかった場合、所得は98万円です。基礎控除額の95万円を超えるため、確定申告が必要です。
なお、専業の場合でも、住民税の申告が求められます。確定申告が不要だからと申告漏れがないようにお気をつけください。
確定申告の準備:まず「開業届」を出そう
クリエイターとして本格的に活動するなら、「開業届」を提出しましょう。
提出は原則、開業日から1ヶ月以内が目安ですが、実務上は事業を開始したと判断できる時点での提出でも認められます。
「持参」「郵送」「e-Tax」の3種類の提出方法がありますが、データを送信した受信通知が従来の開業届の控えとして利用できるので、e-Taxを利用するのがおすすめです。
なお、その際にあわせて「青色申告申請承認書」を提出すると、確定申告で青色申告ができるようになります。最大65万円の特別控除や赤字の3年繰越などの節税メリットを得られるのが利点です。
ただし、青色申告をするには、複式簿記の帳簿と領収書・請求書の適切な保存が必須です。会計ソフトを使い、日々の取引を処理しておくようにしましょう。
【経費】クリエイターの経費にできるもの一覧
確定申告における最大の節税方法は「経費の計上」です。経費とは、事業を行うために必要な支出を指します。
もちろんプライベートな支出は含まれませんが、業務との関連性をきちんと説明できれば幅広く認められます。
クリエイター活動では、次のような項目が代表的です。
・制作機材やソフトウェア代(PC・ペンタブ・編集ソフトなど)
・資料購入費(画集・専門書・動画配信サービス利用料など)
・家賃・光熱費・通信費の一部(自宅兼事務所の場合は按分)
・交通費や宿泊費(取材やイベント参加にかかる費用)
・撮影機材や消耗品(カメラ、三脚、インク、コピー用紙など)
プライベート利用するものについては「業務使用割合」を明確にしてください。たとえば、自宅の家賃を経費にする場合、仕事で使用している部屋の面積や使用時間の割合を根拠にして按分します。インターネット回線やスマートフォン料金も、私用分を除いて業務利用分を計算することが必要です。
また、顧客との外食や打ち合わせでの飲食費は「会議費」として認められる場合があります。しかし、業務と関係のない家族や友人との食事は対象外です。
こうしたグレーゾーンを無理に経費にすると、税務調査を受けた際に、税務署から否認され追加徴税となるリスクが高まります。一方で、正当に認められる経費計上を漏らすと、不要な税負担を背負うことになります。領収書やレシートを必ず保管し、日々の支出を会計ソフトで記録しておくことが安心につながります。
クリエイターが税理士(会計事務所)に相談するメリット
クリエイター固有の問題として、動画配信の収益やクラウドソーシングの報酬など、プラットフォームごとに源泉徴収や振込形態が異なることがあげられます。
プラットフォームごとに計上方法を変える必要があるものの、これが正解なのかわからないと不安になるでしょう。そのようなとき、税理士や会計事務所を頼ることで、以下のようなメリットを享受できます。
・申告書類を正確に作成でき、申告漏れやペナルティを回避できる
・節税のアドバイスを得られ、青色申告の特典を最大限に活用できる
・経費の範囲や仕訳方法など、判断に迷いやすい論点を相談できる
・事務作業を委託できるため、制作や営業に集中できる
特にクリエイターならではの実務に精通した税理士であれば、トラブルを未然に防げるのがポイントです。
また、クリエイターが直面する税金は所得税だけではなく、住民税・消費税・個人事業税などがあります。中でも消費税は、インボイス制度を利用するかの判断も必要です。活動方針に沿ってどう選択するのがいいのかを専門家に相談するのが賢明といえます。
ほかにも、税務はもちろん、売上が伸び始めたタイミングで法人化を検討する際にも役立ちます。法人化するメリットもデメリットもあるため、どちらの側面も理解した専門家から根拠を持って提案してもらえると選択しやすくなるでしょう。
しかし、税理士にも得意分野があります。税務の専門家だからと闇雲に選ぶのではなく、自身の職業に強い税理士や会計事務所を探すのがおすすめです。同じような事例を数多く扱っていれば、過去の経験からよりよいサポートを提供してくれるため安心して任せられます。
クリエイターが利用できる補助金や助成金の申請サポート、動画機材やイラストソフトの経費処理方法など、クリエイター独自の悩みに寄り添ってくれるのは心強いでしょう。
税務にかける時間とストレスが大幅に減り、本業である創作活動に専念できるのが最大のメリットです。
まとめ

クリエイターが安心して創作活動を続けるには、確定申告の基本を押さえることが欠かせません。まずは「開業届」を提出して青色申告の準備を整え、日々の経費を会計ソフトで管理する習慣を身につけましょう。
そして、経費の範囲を正しく理解し、税務上のリスクを避けることが重要です。
しかし、はじめて確定申告をするのなら、記帳方法や申告手順で迷う方は多いでしょう。そのような方は、クリエイターに強い税理士へ相談することを検討してみてはいかがでしょうか。
田中貴久公認会計士事務所なら、漫画家やイラストレーター、Youtuberなどのクリエイターの方をサポートしてきた実績が豊富です。税務でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。