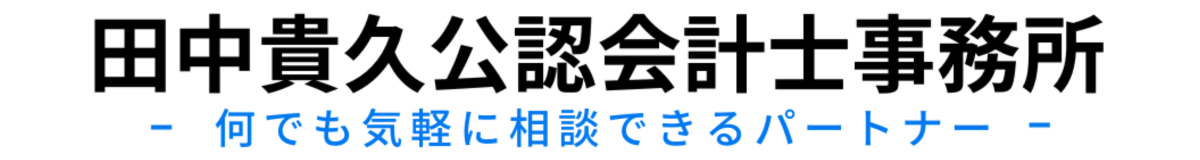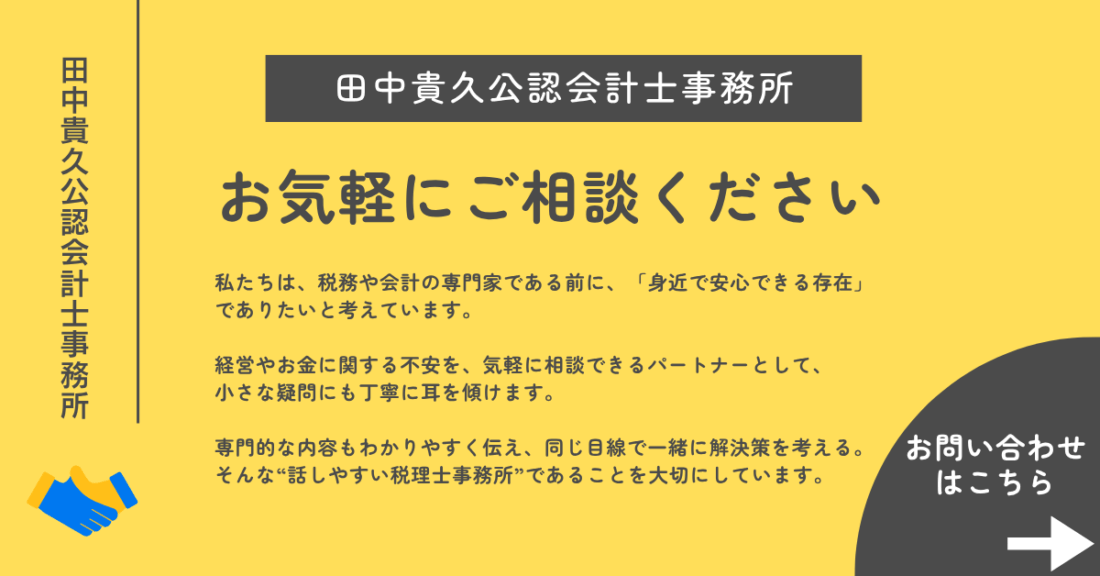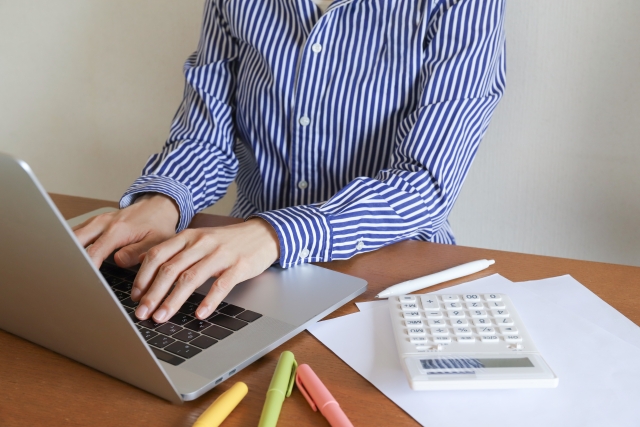
副業やフリーランスとして収入を得ている人にとって、確定申告は避けて通れません。とくに「青色申告」は、節税効果の高さから多くの個人事業主が選んでいます。
本記事では、白色申告との違いから、最大65万円の控除を受けるための条件やメリットまで、わかりやすく解説します。
青色申告と白色申告の違いを解説
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、事前申請が不要で、簡易的な帳簿(単式簿記)を付けるだけで済む方法です。手続きの手間が少ないため初心者でも始めやすい一方、控除額が少なく、節税の効果はほとんどありません。
一方、青色申告は税務署への「青色申告承認申請書」の提出が必要で、複式簿記による記帳が求められます。しかし、その分、最大65万円の特別控除をはじめとした多くの税制優遇を受けることが可能です。会計ソフトを使えば複式簿記の処理も自動化できるため、初心者でも青色申告がしやすくなっています。
青色申告を選択するメリット4選
青色申告の最大の魅力は、税金を大きく節約できる点です。具体的なメリットを4つに分けて見ていきましょう。
1.最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告を行うと、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」が受けられます。この控除は、複式簿記で帳簿を付け、確定申告書を期限内に提出し、e-Taxまたは電子帳簿保存に対応していることが条件です。
控除額が大きいため、課税所得が減り、その分だけ所得税や住民税が軽減されます。仮に所得が300万円なら、控除によって年間10万円以上の税金が減るケースもあります。節税効果を狙うなら、青色申告の活用がおすすめです。
2.赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、赤字が出た年の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字と相殺できます。たとえば開業初年度に赤字100万円、翌年黒字100万円の場合、課税対象はゼロとなります。
この「純損失の繰越控除」は、白色申告では適用されないため、事業が軌道に乗るまでの期間を支える強力な制度です。
3.30万円未満の資産を一括で経費にできる
青色申告者は「少額減価償却資産の特例」を利用できます。通常は10万円を超える設備や機材は数年かけて減価償却しますが、この特例により、30万円未満の資産を購入した年に全額経費計上できます。
例えば20万円のパソコンを買った場合、通常なら数年に分けて経費化しますが、この制度を使えば購入年に全額を経費として処理可能です。クリエイターやフリーランスにとっては、初期投資の負担を軽減しつつ節税できるメリットがあります。
4.家族への給与を経費にできる
青色申告者は、事業を手伝う家族への給与を経費として計上できます。これを「青色事業専従者給与」といい、適正な金額を設定すれば、その分所得が減り、税負担が軽くなります。
例えば配偶者に月10万円支払う場合、その金額は全額経費扱いとなり、結果的に課税所得が減ります。白色申告では「専従者控除」として上限が設けられていますが、青色申告なら支払額に制限がないことがメリットです。
青色申告を始めるための流れを3ステップで解説
青色申告を行うためには、いくつかの手続きが必要です。とはいえ、難しい作業はほとんどありません。ここでは、初心者でもスムーズに青色申告を始められる3つのステップを紹介します。
1.税務署に「開業届」を提出する
まずは税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。住所地を管轄する税務署に、持参・郵送・e-Taxのいずれでも提出可能です。
従来は窓口に行けば受領印が貰えて銀行口座の開設やクレカ審査で控えを提示することで手続きができましたが、現在受領印を押す運用は廃止されています。そのかわりとして、e-Taxで申告等データの送信が完了した後に送られてくる、データの受信通知を利用することがおすすめです。
BOOTHやSkeb等で継続収入があるクリエイターも、早めの届出をしておくと安心です。提出は通年可能ですが、事業開始から速やかに行うと収支の区分が明確になります。開業届は青色申告の前提ではありませんが、同時に提出すると書類管理が楽です。提出控えは大切に保管し、後日の証明に備えましょう。
2.「青色申告承認申請書」を提出する
青色申告を利用するには「青色申告承認申請書」の提出が必須です。原則、開業日から2か月以内、既存事業者はその年の3月15日までが期限です。開業届と同時提出が最も確実で、失念防止になります。
freeeや弥生には申請書の自動作成機能があり、e-Tax送信にも対応します。期限後は当年の青色適用ができず白色扱いとなるため、締切管理が重要です。あわせて、青色事業専従者給与の届出も検討すると、家族への給与経費化が円滑です。
疑問点は税務署窓口かチャットサポートで早めに解消し、漏れを防止しましょう。
3.帳簿を付けて収支を管理する
日々の取引を複式簿記で記録し、領収書・請求書の保存を徹底します。銀行口座とクレジットカードを事業用に分け、会計ソフトへ自動連携すると仕訳が効率化します。
65万円控除を狙うなら、複式簿記+期限内申告に加え、e-Tax送信または電子帳簿保存に対応が必要です。月次で試算表を確認し、売上・経費・利益の推移を把握しましょう。
現金取引はレシート撮影で即入力、未収・未払は発生主義で処理します。固定資産は少額減価償却資産の特例を活用し、30万円未満は一括経費を検討してください。期末の棚卸や家事按分も早めに基準を決め、記録を残すと申告時に迷いません。
仕訳の根拠メモを残す習慣をつけると、後日の確認や税務調査でも説明が容易です。
青色申告を検討している人からよくある質問
最後に、青色申告を検討中の人から寄せられる代表的な質問に回答しておきます。
Q1.白色申告から青色申告に切り替えられますか?
白色から青色への切替は可能です。切替えたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出すれば、原則その年分から青色の適用が受けられます。
開業から2か月以内の新規事業者は、その期限が優先されます。申請は一度のみで、毎年の更新は不要です。翌年以降にやめたい場合は取りやめの届出で白色へ戻せます。申請漏れを防ぐため、開業届との同時提出が最も確実です。
なお、65万円控除を狙う場合は、複式簿記での帳簿付け、期限内申告、e-Tax等の条件も同時に満たす必要があります。控えは必ず保存し、会計ソフトの設定(期首残高や勘定科目)を青色仕様に切替えておきましょう。期中でも運用を整えれば、翌期の申告精度が向上します。
Q2.売上がまだ少ないのですが、青色申告にするメリットはありますか?
売上が少なくても青色のメリットは大きいです。開業初年度は初期投資で赤字になりやすく、青色ならその赤字を3年間繰り越し、翌年以降の黒字と相殺できます。さらに65万円(または55万円)の特別控除で課税所得を圧縮可能です。
会計ソフトを使えば複式簿記の負担も小さく、経営数値の可視化が早期に進みます。少額でも帳簿を継続すれば資金繰りの癖がつき、無駄な支出の発見や価格設定の見直しに役立ちます。白色では赤字繰越が使えないため、成長局面での税負担に差が出ます。
将来の事業拡大を見据えるなら、早期に青色へ移行し、制度の恩恵を最大化するのが合理的です。
まとめ

青色申告は、白色申告に比べて手続きや帳簿付けの手間が増えますが、それ以上に得られる節税効果が魅力です。最大65万円の特別控除や赤字の繰り越し、家族への給与経費化など、長期的な経営を支える制度が充実しています。
難しそうに見えても、会計ソフトの導入で作業は大幅に簡略化できます。しかし、もし手続きにおいて不安を感じた場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
田中貴久公認会計士事務所はクリエイターをはじめとしたフリーランスの確定申告を数多く取り扱っています。どのようなご相談でもお受けしているので、お気軽にお問い合わせください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。